目次
効率的な学習に必要なメタ認知ってなんのこと?

メタ認知とは、自分が「今何を考えているのか」、「何を知っているのか」わかっていることを言います。「認知(わかっている・知っている・考えている)ことを認知している(わかっている)」状態のことを言います。
「メタ」とは、「高次の」という意味です。メタ認知とは、認知(わかっている・知っている)状態を上から俯瞰してみている状態のイメージを持っていただければと思います。自分のわかっていることを上から見ているので、「自分のわかっていることがわかっている」状態なのだと思います。
メタ認知とはどんな状態でしょうか?具体例をあげてみます。
例えば、Aさんがすごくイライラしていて怒っているとします。そのときAさんが「今自分めっちゃ怒ってるなー」と気づければ、メタ認知が出来ていると言えるでしょう。
それ以外にも、大事な面接試験の際に「あ、やべオレめっちゃ緊張してるわ」と気がつけるのもメタ認知が出来ている状態と言えます。というのも、緊張しているという認知活動を客観的に理解しているからです。
実際の勉強への活かし方
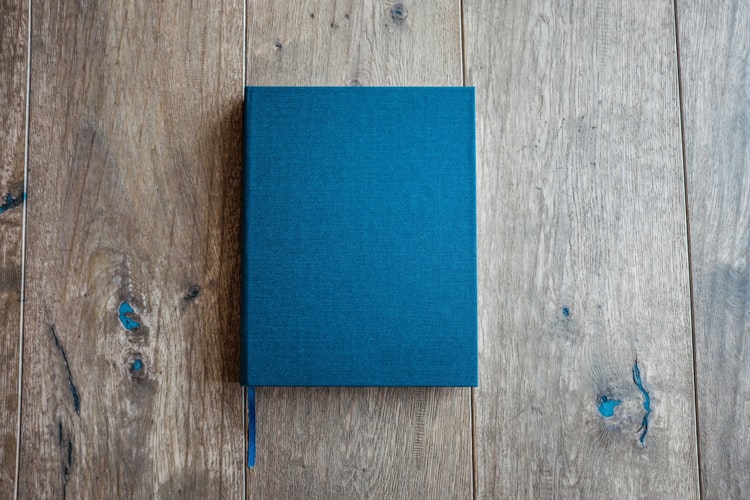
メタ認知の学習の活かし方として、自分の思考や行動を客観的に把握し、認識するという際に使われます。メタ認知を活かした勉強として、簡単に分けて3つのものがあります。順番に説明していきます。
①自己認知(自分について知っている)
自己認知的メタ認知として、自分のことをわかっているという状態です。具体的には、自分がどんな科目が得意で、どんな科目が苦手かなど、簡単に自分の状態がわかっている状態の人のことを言います。
②メタ認知的活動(自分の認知のパターンや自分のしたことを振り返る)
テスト期間にどれだけ勉強をすすめることができるのか、1日にどれくらい自分が勉強するのか想定する力であったり、実際に計画を実行した結果、どれだけ出来たか評価する力や学習の度合いを調整する力もメタ認知と関わってきます。というのも、実際に計画を実行したあと、どれだけ出来たのか、効果はどれくらいあったのか評価する際、良かった点はどんな点だったのか、逆に悪かった点はどんな点だったのか、自分の過去にやっていたものを振り返りながら、評価します。これらもメタ認知能力があるからこそできる行動です。
③メタ認知における制御
自分は英単語や古文単語を暗記する時、どのような暗記方法(例えば、耳で聞きながら暗記する、手でたくさんかくことで暗記するなど)で暗記するのが得意なのか知っている状態も、自分の状態を客観的に把握できているのでメタ認知が出来ている状態と言えます。
※なお自分の得意のスタイルを知っておくことで効率よく学習できます。学習スタイルについては以下の記事が詳しいのでよければ参考にしてみてください。
このように大きく分けて3つの段階のメタ認知の層があります。自分について知っているだけでなく、自分の得意な思考パターンはなにかなどもメタ認知に入ります。
実際の学習場面でもメタ認知は使用されます。自分で問題を解いている際、「そういえばこの前この部分で符号ミスをしてしまったから気をつけなくちゃ」と気をつけながら、問題を解いてみることもメタ認知と関係しています。問題を解いている際、「この公式を使って当てはめていけば良くて、今はこの部分を解いていて…」などと自分が今解いている状況を冷静に判断できるのもメタ認知に関連しています。それだけでなく、「テストで間違えた問題を振り返り、自分が出来なかった理由を分析し、今後どうしたらミスしないか考えること」もメタ認知を活かして勉強できています。
科学的根拠
メタ認知の研究はいくつかの領域ですでに報告されています。算数分野では、Schoenfe1d(1985)の実践が良く説明に利用されます。Schoenfe1d は、ヒューリステイックスを利用して、学生相互のモデリングやコーチングを取り入れた学習活動を展開しました。具体的には、まず、教員が問題を解いて見せ、学学生はそれを参考にして別の解決方略を考え出すようにうながされます。生徒たちが、いくつかの解決方略が出てき
たところで、そのうちのどれが実行可能か、どのくらい時間がかかるか、などが検討され、さらに一人一人の学生が、そのやり方が自分にあっているか、その方法を使えるようになるには自分があと何を知らなければならないか、などを自己評価をします。生徒は、このような活動を通して、どんなことを自分がわかっていればよいのかなどを振り返り、主体的に勉強できるようになったという研究も報告されています。
まとめ
メタ認知の能力を向上させることで、自分自身を客観的に見ることができるようになります。自ら目標設定を行って達成する力が身につきます。学習能力をアップするスキルを得られることで、様々な分野で注目されています。
メタ認知能力が低い場合でも、訓練によって固めることが可能です。
早くからメタ認知能力を磨いておけば、大きな変化があった場合でも速やかに適応することができます。
「共に学び合う」 「1人で学ぶ」を繰り返し、 メタ認知能力を高める
山根 嵩史(2016)記憶課題における学習容易性判断に用いられるメタ認知的知識の検討 広島大学大学院教育学研究科紀要 第三部 第65号 149-156
Scardama1ia et a1, (1984) Teachability of reflective processes in writtencomposition, Cognitive Science, 8, 173-190.














