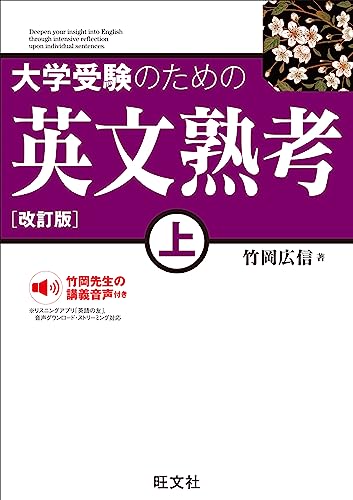
- 参考書名
- 『英文熟考【上】(改訂版)』(旺文社)
- 著者
- 竹岡広信
- 発売日
- 2023/07/19
- ISBN10
- 401035125X
- ページ数
- 本冊151/別冊71
- 科目
- 英語(英文解釈)
- タイプ
- 英文解釈
- ランク
- 標準〜難関ランク
- 所要時間
- 26.5h
目次
『英文熟考【上】(改訂版)』 (26.5h)
目安時間:1時間/1回
英文法のポイントを含む英文を題材に、英文解釈のポイントを詳しく説明した参考書。詳しく丁寧な解説とリスニング音声がついているのが特徴である。本書は比較的基本的な文法テーマを扱っており、『英文熟考【下】(改訂版)』で比較的発展的なテーマを扱っている。
『英文熟考【上】(改訂版)』の進め方
1周目(17.5h)
S01 1.0h 第1回 動詞 1「動詞を見たら他動詞か自動詞かを考える」、2「前置詞のついた名詞は目的語にはならない」、3「過去分詞形の後置修飾に慣れよう①」、4「過去分詞形の後置修飾に慣れよう②」
S02 1.0h 第2回 動詞 5「過去分詞形の後置修飾に慣れよう③」、6「過去分詞形の後置修飾に慣れよう④」+接続詞ほか 7「文と文をつなぐには接続詞が必要」、8「if SVは二通りの可能性を検証しよう」
S03 1.0h 第3回 接続詞ほか 9「whether SVは二通りの可能性を検証しよう①」、10「whether SVは二通りの可能性を検証しよう②」+関係代名詞 11「whatを見たら『名詞の欠落』を探そう①」、12「whatを見たら『名詞の欠落』を探そう②」
S04 1.0h 第4回 関係代名詞 13「whatの後ろにあるhave to(V)の意味」、14「人称代名詞に置き換えて語順どおり読む①」、15「人称代名詞に置き換えて語順どおり読む②」、16「人称代名詞に置き換えて語順どおり読む③」
S05 1.0h 第5回 関係代名詞 17「人称代名詞に置き換えて語順どおり読む④」、18「人称代名詞に置き換えて語順どおり読む⑤」、19「『焦点化』された形を元に戻して訳す」、20「名詞が連続していたら関係代名詞の省略の合図①」
S06 1.0h 第6回 関係代名詞 21「名詞が連続していたら関係代名詞の省略の合図②」、22「名詞が連続していたら関係代名詞の省略の合図③」、23「名詞が連続していたら関係代名詞の省略の合図④」、24「名詞が連続していたら関係代名詞の省略の合図⑤」
S07 1.0h 第7回 関係代名詞 25「名詞が連続していたら関係代名詞の省略の合図⑥」+接続詞ほか 26「後続の文を一つの名詞節にまとめる that」、27「that節は主語になる①」、28「that節は主語になる②」
S08 1.0h 第8回 接続詞ほか 29「that節は補語になる①」、30「that節は補語になる②」、31「that節中の副詞節の挿入①」、32「that節中の副詞節の挿入②」
S09 1.0h 第9回 接続詞ほか 33「that節中の副詞節の挿入③」、34「名詞と that節の『同格関係』①」、35「名詞と that節の『同格関係』②」、36「so / suchを見たらthatを探そう①」
S10 1.0h 第10回 接続詞ほか 37「so / suchを見たらthatを探そう②」、38「so / suchを見たらthatを探そう③」、39「so / suchを見たらthatを探そう④」、40「thatが関係代各詞か接続詞かの識別」
S11 1.0h 第11回 不定詞 41「to (V)~のtoは『まとめ役』①」、42「for~to (V)は『~がVする』①」、43「for~to (V)は『~がVする』②」+動名詞 44「(V)ing~の-ingは『まとめ役』①」
S12 1.0h 第12回 不定詞 45「to (V)~のtoは『まとめ役』②」+動名詞 46「(V)ing~の-ingは『まとめ役』②」、47「《前置詞+名詞+(V)ing》は二通りの可能性を検証しよう①」、48「《前置詞+名詞+(V)ing》は二通りの可能性を検証しよう②」
S13 1.0h 第13回 分詞構文 49「文末の分詞構文は主文の具体化・補足」、50「過去分詞で始まれば受動態の分詞構文を考えよう」、51「主語の直後の分詞構文は『両側にコンマ』が目印、52「形容詞で始まる分詞構文に慣れよう」
S14 1.0h 第14回 分詞構文 53「副詞句の名詞+(V)ingは独立分詞構文の可能性①」、54「副詞句の名詞+(V)ingは独立分詞構文の可能性②」、55「副詞句の名詞+(V)ingは独立分詞構文の可能性③」+挿入 56「ダッシュ(一)による副詞の挿入」
S15 1.0h 第15回 接続詞ほか 57「セミコロン(;)の働き」+倒置 58「《場所を示す副詞》+VSの倒置」、59「文頭の否定的副詞(句・節)は倒置の合図」、60「A and / but / or BのAとBは等しい形①」
S16 1.0h 第16回 接続詞ほか 61「A and / but / or BのAとBは等しい形②」、62「A and / but / or BのAとBは等しい形③」、63「A and / but / or BのAとBは等しい形④」、64「A and / but / or BのAとBは等しい形⑤」
S17 1.0h 第17回 接続詞ほか 65「A, and B, ~の“~”は共通の要素」、66「A, or B, ~の“~”は共通の要素」、67「《A and 副詞 B》の副詞の挿入①」、68「《A and 副詞 B》の副詞の挿入②」
S18 0.5h 第18回 接続詞ほか 69「《A or 副詞 B》の副詞の挿入」、70「neither A nor B のAとBは等しい形」
2周目(9h)
S19 0.5h 第1回 動詞(1~4)
S20 0.5h 第2回 動詞、接続詞ほか(5~8)
S21 0.5h 第3回 接続詞ほか、関係代名詞(9~12)
S22 0.5h 第4回 関係代名詞(13~16)
S23 0.5h 第5回 関係代名詞(17~20)
S24 0.5h 第6回 関係代名詞(21~24)
S25 0.5h 第7回 関係代名詞、接続詞ほか(25~28)
S26 0.5h 第8回 接続詞ほか(29~32)
S27 0.5h 第9回 接続詞ほか(33~36)
S28 0.5h 第10回 接続詞ほか(37~40)
S29 0.5h 第11回 不定詞、動名詞(41~44)
S30 0.5h 第12回 不定詞、動名詞(45~48)
S31 0.5h 第13回 分詞構文(49~52)
S32 0.5h 第14回 分詞構文、挿入(53~56)
S33 0.5h 第15回 接続詞ほか、倒置(57~60)
S34 0.5h 第16回 接続詞ほか(61~64)
S35 0.5h 第17回 接続詞ほか(65~68)
S36 0.5h 第18回 接続詞ほか(69~70)
3~5周目(4.5h×3)
0.5h 第1-2回 動詞、接続詞ほか(1~8)
0.5h 第3-4回 接続詞ほか、関係代名詞(9~16)
0.5h 第5-6回 関係代名詞(17~24)
0.5h 第7-8回 関係代名詞、接続詞ほか(25~32)
0.5h 第9-10回 接続詞ほか(33~40)
0.5h 第11-12回 不定詞、動名詞(41~48)
0.5h 第13-14回 分詞構文、挿入(49~56)
0.5h 第15-16回 接続詞ほか、倒置(57~64)
0.5h 第17-18回 接続詞ほか(65~70)
『英文熟考【上】(改訂版)』の取り組み方
※別冊の「熟考編」を周回数分コピーする。
1~5周目の学習の流れ
<1・2周目> ①別冊「熟考編」の英文を和訳する。(目安時間:1周目5分、2周目3~4分/1題) ②各テーマの解説を通読し和訳を添削する。(目安時間:1周目10分、2周目3~4分/1題) ③次のCHAPTERに進み、①~②を繰り返す。 <3~5周目>1・2周目で十分に英文解釈の知識やプロセスを習得出来なかった人向け ④別冊「熟考編」の英文を掲載されている順番で一通り音読するのを各10回繰り返す。(目安時間:15分) |
1・2周目 S01-18, S19-36
①別冊「熟考編」の英文を和訳する。(目安時間:1周目5分、2周目3~4分/1題)
※英文にSVOCを振りながら、コピーした別冊の「熟考編」で実際に和訳を書いてみる。分析した英文の構造がきちんと日本語に反映できているか、文の意味を伝えることができているかを意識すると良い。◀文構造分析の通りに忠実に和訳をすることで分析の間違いに気づける場合があるため。意味の通らない文になった場合は構造分析に間違いがないか見直そう。
※「語句チェック」で分からない単語や表現を参照したり辞書を引きたい場合は、必ず構造把握の後に行う。◀まずは意味をとるよりも文構造の分析が優先であるため。辞書を引く前に文脈や文構造から類推して解くよう心がける。
※和訳した文が不自然な場合意訳をして文章全体の意味やニュアンスが伝わる訳になるよう心がける。◀難関大学の入試では文構造の分析が間違いなくできたうえで自然な和訳ができているかの日本語力を見ている場合が多いため、練習を積んでおく。
※2周目では1周目で間違えた問題を中心に和訳を行う。この際自分が間違えた箇所を意識し、解説を思い出しながら日本語に訳す。◀間違えた箇所が自分の中で理解できており、繰り返し間違わないことが重要であるため。
②本冊「解答・解説編」の各テーマの解説を通読し和訳を添削する。(目安時間:1周目10分、2周目3~4分/1題)
※自分が作った和訳と和訳例を照らし合わせるとき、和訳が似ているかどうかではなく、英文を見たときの考え方・構造分析の方法が解説と合っているかを確認する。◀構造分析が正しくできていないと正しい和訳も作れないため。
※特に解答が間違っていた場合はもちろん合っていた場合も必ず「英文分析」を読む。◀文に対する理解が合っているか確認できることはもちろん、英文解釈で役立つ知識が掲載されているため。
※この際、情報を書き込む場合やメモを取る際は、本書に直接書き込むこと。
※文面での解説が分かりずらいと感じたら講義音声を聞くことで、理解を徹底する。
※訳例の注釈は必ずチェックし、各テーマで紹介されている単語や表現は必ず暗記すること。◀英文解釈の問題では入試において頻出の表現や文法事項が限られているため、暗記することで得点に直結する場合が多いため。
③次のテーマに進み、①から繰り返す。
3~5周目
④上記の進め方の範囲に沿って、別冊「熟考編」の英文を掲載されている順番で一通り音読するのを各10回繰り返す。(目安時間:15分)◀1・2周目で文構造分析による和訳のプロセスが習得しきれなかった場合、3周目以降では音読によるアプローチで学習を継続する。(30回音読をすることで、文構造を分析するプロセスを英文と合わせて定着させる。)
※この際、スピードを意識する。「自分が本番で読むときの理想のスピード」を目標に、自分が理解できる範囲でのMAXのスピードに徐々に近づけていくイメージで読む。◀スピードを意識することで速読力が身につくためである。
※英文を理解することが最優先であるため、日本語訳と照らし合わせながら、英文の内容や構造・意味が取れるようになるまで音読する。
英語の参考書分析一覧に戻る
各科目の参考書分析









