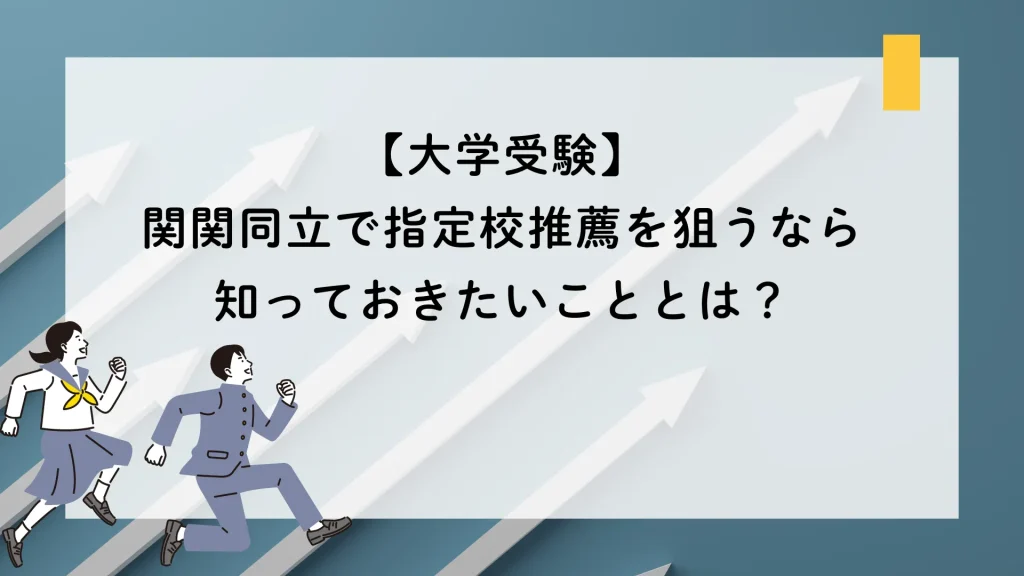大学受験を考えたとき、指定校推薦について考えたことはあるでしょうか。大学入試は大きく3つに分けられます。一般入試、公募推薦、そして指定校推薦です。なんだか仕組みが難しそう、指定校推薦の対策をしていると学力を落とすんじゃないかなど、思っている方も多いと思いますが、この記事では難関私立校である関関同立の指定校推薦を考えている人に向けて、公募推薦との違いや、メリットとデメリット、試験内容や、今から対策しておいたほうが良いことについてお伝えしていきます。
目次
関関同立の指定校推薦枠とは?
結論から申し上げますと、関関同立で指定校推薦について募集要項は公開されていません。まずは自分の学校の進路担当の先生に聞いてみましょう。また、去年まで指定校推薦があったからと言って、今年も指定校推薦枠があるとは限りません。先生に聞いて確実な情報を知っておきましょう。その理由として、過去に指定校推薦で入った学生の成績が芳しくなかったりすると、枠が減らされたり、取り消されたりすることがあるためです。そのため、ただでさえ少ない指定校推薦の枠なので、無くなることもありえます。
公募推薦との違い
指定校推薦とともによく耳にするのが同じ学校推薦型選抜である「公募推薦」ではないでしょうか。どちらも学校推薦型選抜といっても大きな違いがあります。指定校推薦とは、大学が指定した高校の生徒にのみ出願資格があります。そして、最大の強みはほぼ確実に合格できる点です。その一方で公募推薦は、大学の定めている出願条件を満たし、校長の推薦があれば、全国のどの高校からも出願できるのが特徴です。そのため、指定校推薦がほぼ確実に合格できるのに対し、公募推薦は、学部によっては高い倍率を潜り抜けなければならず、不合格になる可能性も高いです。
関関同立の指定校推薦を考えるなら知っておきたいこと
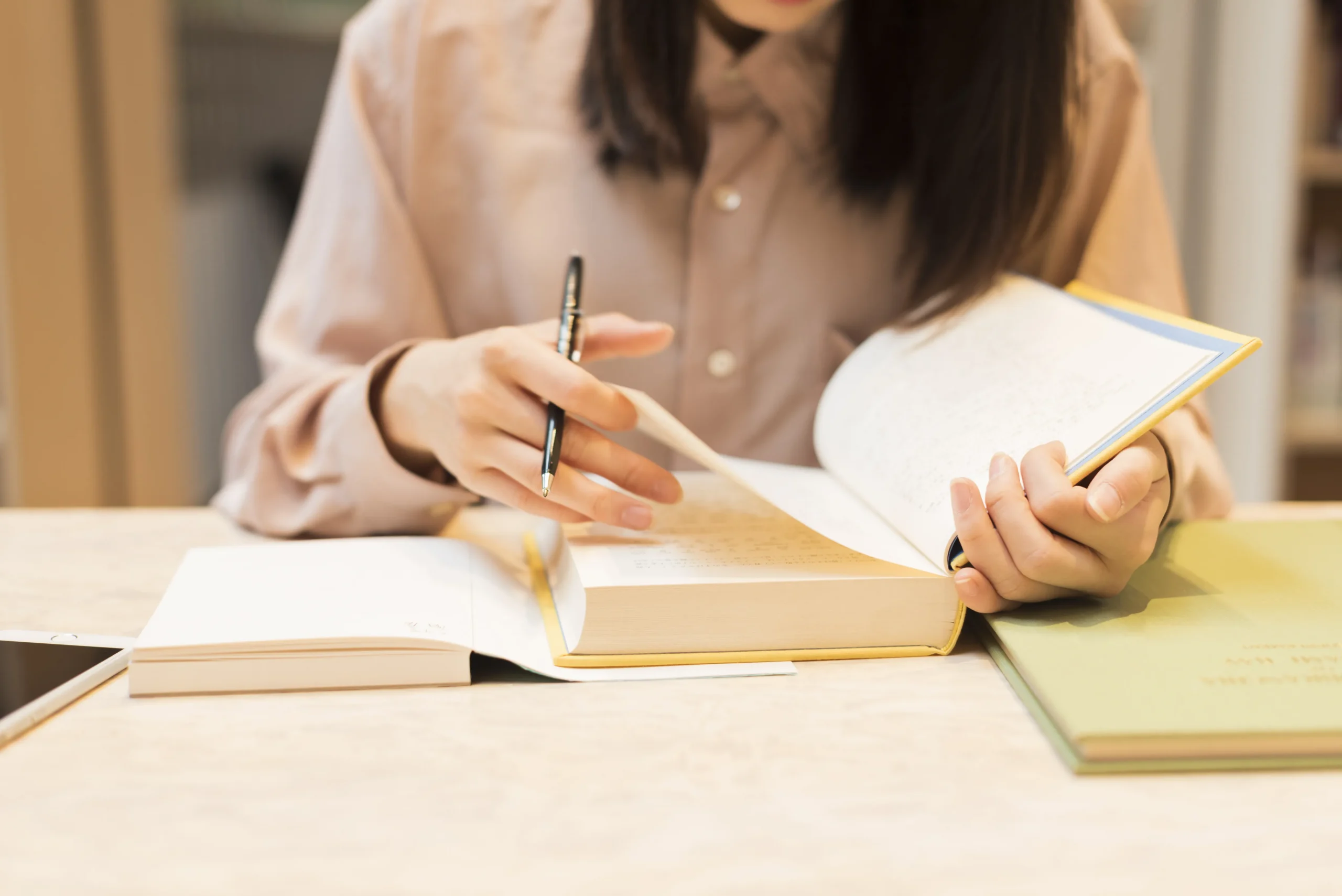
関関同立にかかわらず指定校受験を考えている人であれば、まず知っておきたい流れや判断基準、いつから対策した方がよいのかなどについてお伝えしていきます。
流れ
出願時期や選考の時期は大学によって異なりますが、一般的な流れとしては6~8月頃に各学校にて公開され、校内選考が行われます。10月頃までには推薦される生徒の選抜があり、その後出願が行われます。出願は10~11月頃に行われ、選考では面接や小論文などを実施し、12月には合格発表がされます。
評定平均で判断する
指定校推薦では基本的に評定平均で判断されます。5段階評価で最低でも3.5以上。上位校を狙うのであれば、5をとっていかないと出願基準を満たせません。そのため、公募推薦と同様、高校入学後から大学受験が始まっているという気持ちでもって、授業や定期試験などに取り組み、成績を保つ必要があります。
いつまでの成績が使われるのか
出願資格となる評定平均ですが、高校1年の1学期(前期)から高校3年の1学期(前期)までの評定を参考にします。算出方法は履修した科目の5段階評価の成績を合計し、科目数で割って算出します。
いつから対策をしておいた方がいいのか
出願資格となる評定平均に影響してくるのが、高校1年から高校3年の1学期までの定期試験の結果です。この期間に実施される定期試験は合計で12回(2期制の場合は10回)です。しかもそのうちの5回(2期制の場合4回)の定期試験は高校1年生の時に実施されるものです。つまり、評定平均に占める高校1年生の定期テストの割合は4割を占めます。同じように高校2年も1年間が判断材料になるわけですから、高校2年までに8割が決まっているといっても過言ではありません。そのため、高校3年生になってから評定平均の巻き返しを狙っても困難を極めます。
欠席日数
また、出願条件に欠席日数に指定がある場合があります。大学側に指定はなくとも同級生で、同じ大学の指定校を狙っている生徒がいる場合、校内選考で欠席日数が少ない方に有利に働く傾向があります。
試験内容
志望理由書を課す大学が少ない一方で、申込書などに志望動機や自己推薦書などを記載することがあります。また面接では受験者の人間性や、大学進学に向けての意欲など、学力以外の因子について評価されていきます。それに加え小論文があります。
関関同立で指定校推薦を実施している学部一覧
関関同立における学校推薦型選抜の指定校制は、一部の学部でのみ行われており、2024年度に募集している学部は次の通りです。なお、関西学院大学については2023年度の実績となります。
| 関西学院大学 | 神学部 |
| 文学部 | |
| 社会学部 | |
| 法学部 | |
| 経済学部 | |
| 商学部 | |
| 総合政策学部 | |
| 人間福祉学部 | |
| 教育学部 | |
| 国際学部 | |
| 理学部 | |
| 工学部 | |
| 生命環境学部 | |
| 建築学部 | |
| 関西大学 | 商学部 |
| 環境都市工学部 | |
| システム理工学部 | |
| 化学生命工学部 | |
| 同志社大学 | 神学部 |
| 文学部 | |
| 経済学部 | |
| 法学部 | |
| 社会学部 | |
| 文化情報学部 | |
| グローバル地域文化学部 | |
| グローバル・コミュニケーション学部 | |
| 心理学部 | |
| スポーツ健康科学部 | |
| 立命館大学 | 法学部 |
| 経済学部 | |
| 経営学部 | |
| 産業社会学部 | |
| 文学部 | |
| 国際関係学部 | |
| 政策科学部 | |
| 映像学部 | |
| スポーツ健康科学部 | |
| 総合心理学部 | |
| グローバル教養学部 | |
| 食マネジメント学部 | |
| 理工学部 | |
| 情報理工学部 | |
| 薬学部 | |
| 生命科学部 |
指定校推薦で関関同立への進学を考えるべき人とは?
学校推薦型選抜(指定校制)は、関関同立への進学を目指す多くの受験生にとって魅力的な選択肢です。しかし、どのような人がこの推薦制度を利用すべきか、慎重に考える必要があります。以下に、指定校推薦を活用して関関同立への進学を考えるべき人の特徴をまとめました。
成績が安定している人
指定校推薦を受けるためには、在学中の成績が一定の基準を満たしている必要があります。定期テストや内申点の結果が安定しており、学内で推薦枠を獲得できる見込みがある人は、指定校推薦を積極的に考えるべきです。一般入試よりも競争率が低く、合格の可能性が高いため、志望校への道を確実にしたい場合に有効です。
志望学部が明確である人
指定校推薦は、特定の学部・学科に進学するための推薦です。志望学部や将来の進路が明確で、すでに進みたい分野がはっきりしている人には向いています。推薦枠が決まっているため、一般受験のように複数の学部に出願することはできませんが、第一志望が固まっている人にとっては強力な選択肢となります。
大学での学びや活動に積極的な人
指定校推薦で入学した場合、大学側は学業や課外活動で積極的に活躍することを期待しています。入試のプレッシャーから解放された分、入学後の学習や活動に専念できる環境が整っているため、大学生活を充実させたいという意欲のある人におすすめです。
一般入試に不安を感じる人
一般入試では、試験本番でのパフォーマンスが重要になります。試験のプレッシャーや競争に対して不安がある場合、指定校推薦はリスクを減らして大学に進学できる手段です。推薦枠を活用することで、早期に進路を決定し、精神的な負担を軽減することができます。
これらの要素に当てはまる人は、関関同立への進学を確実にするために、学校推薦型選抜(指定校制)を積極的に検討してみると良いでしょう。
指定校推薦のメリットとデメリット
それでは、指定校推薦のメリットやデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。それぞれお伝えしていきます。
指定校推薦のメリットとは
合格率が高い
受験前に問題を起こしたり、受験当日に寝坊して遅刻するようなことさえなければ、ほぼ確実に合格できるとされています。というのも、大学と高校の信頼関係のもと成り立っている仕組みであるためです。大学側は優秀な人材を求めて、この高校であったら優秀な生徒がいるであろう。高校側としては何とかして生徒を送り出したい。そういった利害の一致があって成り立っているためです。そのため、まず落ちることはないと考えられます。ただ、医学部や看護学部などは、人間性などもみられますので確実ではありません。
合格発表が早い
11~12月頃には結果が分かるので、公募推薦と同じく、一般入試よりも早く結果が分かります。一般入試だと早くても年明け2月頃になります。一般入試より、2カ月近く早く結果が分かります。そのため、余裕をもって入学準備などをすることが可能です。
一般受験より費用を節約できる
指定校推薦は高校2年までの成績で評定が8割決まってきます。学校の試験対策を行っていればよいので、特に予備校に通う必要性はありません。そのため、費用は抑えることができます。その一方で、一般入試に向けて勉強している人は予備校の費用や教材費、受験費用、交通費など多額な費用が掛かってきます。これより、一般入試より指定校推薦の方が費用を抑えられることが分かります。
自分の実力以上のところにも行ける可能性がある
一般入試では試験の点数のみで評価されますが、指定校推薦は高校の評定平均で判断されます。定期試験ではいい点数が取れても、模試ではいい点数が取れない。そんな経験がある人も決して少なくはないのでしょうか。学校の定期試験は範囲が決まっています。一方、模試は範囲が広く、応用問題なども出てきます。そのため、評定は良くても偏差値はそこまでいかない人にとって、指定校推薦は非常に魅力的です。評定が良ければ、自分の偏差値以上の大学に行くことも可能だからです。
指定校推薦のデメリットとは
枠が少なく学選抜が厳しい
指定校推薦枠は1~数名程度です。また年によっては無くなることもあります。貴重な推薦枠をより優秀な生徒に割り振るために厳しい校内選考が行われます。評定平均はもとより、日々の授業態度や部活動、委員会活動、生徒会活動、課外活動などの加点ポイントも重要になってくるため、その中で推薦枠を勝ち取るのは非常に大変です。
一般入試組に学力が及ばない可能性がある
指定校推薦では、自分の実力以上の大学に入学できる可能性があります。仮に入学できた場合、入学時は特に一般入試組と足並みを揃えるための学力を補っていかなければなりません。早く合格したからといって安心せず、勉強をしていきましょう。
国公立はまず実施していない
指定校推薦は私立大学で活用されている仕組みであり、国公立大学を目指している場合は一般入試か公募入試のみのところが大半なので、注意が必要です。
専願である
指定校推薦は専願であり併願が出来ません。第一志望が他の大学であった場合は、指定校推薦を受けてしまうと、受験できなくなってしまうため注意が必要です。
中退が難しい
指定校推薦とは、大学と高校の信頼関係があって成り立つ入試制度です。出身校を代表して入学しているため、大学側は期待すると同時に〇〇高校の生徒としてチェック対象にもなっています。高校卒業後も出身校の代表として見られています。そのため、その学生の動向次第では推薦枠の削減や消滅に繋がりかねません。その結果、模範的であることを暗に求められ、中退は難しくなります。
関関同立の指定校推薦の試験内容と対策
関関同立の指定校推薦の試験内容
ここまでお伝えしてきたように、指定校推薦については一般に公開されていません。そのため、詳細については学校の先生に確認をとってみましょう。学校内でデータを集めていることがほとんどですが、おおむね志望理由書、面接、小論文があるのが一般的です。
今からやっておくべき対策方法
定期試験対策をしよう
入学直後からすぐに勉強習慣を身に着け、授業態度や定期テストの結果を良くしていきましょう。わからないことはそのままにせず、学校の先生に聞いてみましょう。
できるだけ出席しよう
欠席日数は校内選考で評価の対象になることがあります。欠席・遅刻・早退は少なくして、できるだけ出席しましょう。
勉強以外の活動も頑張ろう
校内選考で評価の対象になるので、部活動や委員会活動、課外活動などにも取り組み、評価対象を増やしていきましょう。
指定校推薦が取れない場合の対策もしよう
指定校推薦を希望する生徒は多いです。そのため指定校推薦の枠を取れない可能性もあります。日頃からそれ以外でも入学できる可能性を広げましょう。関関同立の公募推薦を狙ったり、AO推薦、一般入試、それぞれ対策を取りましょう。指定校推薦を考えていたならば、公募推薦や、AO入試が狙い目です。
公募推薦では、立命館大学など実施していない大学もありますが、同志社大学などでは、出願条件がとても厳しくハードルが高いため、出願条件さえクリアしていれば、学部によっては受かりやすいです。また、AO入試も指定校推薦と同じく選考内容が面接と小論文のことが多いため対策がしやすいです。最後に一般入試ですが、万が一それでも厳しかった場合のことも考えて、一般入試の対策もしていきましょう。
まとめ
最後に、指定校推薦は多くの学生が取得したいと思う入試方法です。嬉しい気持ちもわかりますが、指定校推薦が決まった際は同級生の間で口外しないようにしましょう。周りには指定校推薦をとりたかった人もいますし、一般入試のために必死に勉強している同級生ばかりです。数少ない枠を取れたことは特別なことです。受かったことは同級生に口外せず、入学に向けて、学力を落とさないように勉強をしましょう。この記事をもとに関関同立に限らず、指定校推薦を考えている人はお役立てください。