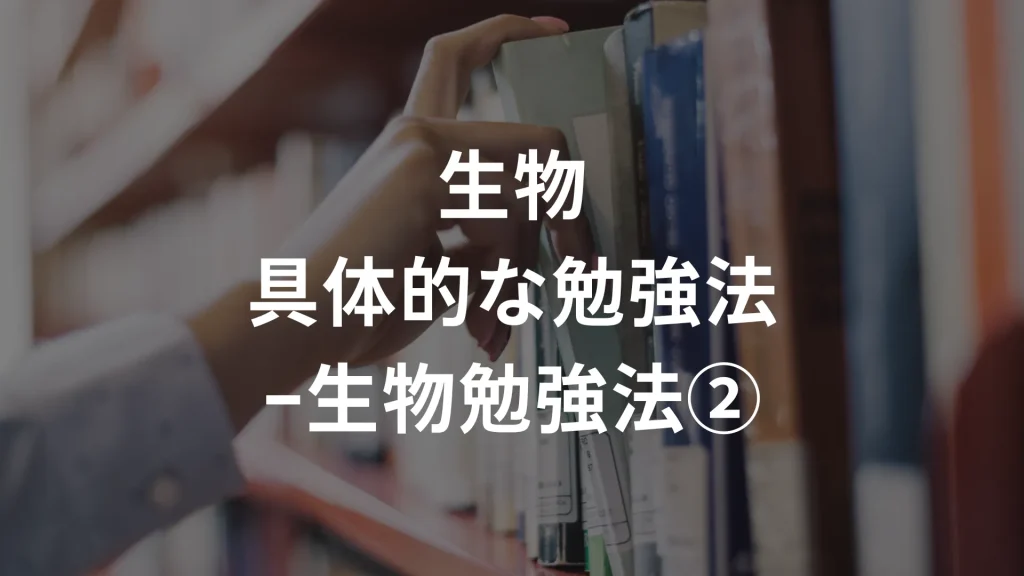目次
生物を勉強する基本的な流れ
学習の3ステップ
❶ 基礎知識のインプット
:基本事項を理解するための参考書(理解本)・教科書・資料集 など
❷習得した基礎知識をもとに問題を解く力を養う
:問題形式や分野に特化したもの、総合的な力を問うものなど、様々な切り口の問題集(演習本)を活用することで、基礎知識をもとに問題を解く力を効果的に養います。
❸ 過去問に挑戦/ハイレベル理解本・演習本に移行
生物の学習方針
生物の学習は、理解本と演習本の2冊で完結できます。
早めに理解本でインプットを終わらせて、演習本で繰り返し実践的な問題を解きましょう。分野ごとに理解本と演習本を行き来して学習するのも効果的です。
時期・レベルによる学習戦略
難関大学を目指す生徒にとって、生物の学習を早期に始めることが非常に重要です。学校の授業を活用しつつも、最終的には授業の進度を追い越して学習を進めないと、受験準備が間に合わなくなる可能性があります。そのため、できる限り早く生物基礎から生物に移行し、効率よく学習を進めることを推奨します。
定期テストを利用する場合、テスト前に演習本で関連項目を復習し、取りこぼしを防ぐよう努めましょう。また、受験勉強開始時に生物基礎で遅れがある場合は、他の学習と並行して学び、早期に追いつくことが大切です。
受験勉強開始が高2・高3であっても、長期休みなどを活用して、理科全体を後回しにしないようにしましょう。
医学部を除く難関ランクまでを目指す場合
高3の夏休み前に演習本1を終え、過去問演習に移行するのが理想です。過去問演習を通して志望校の出題傾向を把握し、必要に応じて対策を進めます。この目安より遅れている場合は、理解本や演習本を完璧に仕上げることにこだわりすぎず、過去問に一度挑戦するのも有効です。
最難関・難関医学部を目指す場合
高2の冬から高3の夏にかけて演習本2や教科書より難しい内容に特化したハイレベル理解本を用いて苦手分野を補強し、高3の夏以降は過去問演習に移行することが理想です。時間が足りない場合は、早めに過去問演習に取り組み、演習本2やハイレベル理解本で必要に応じて補強を行いましょう。全体的に時間が限られているため、学習ペースを目安時間よりも落とさず、効率を重視した学習を心がけることが重要です。
学校で習った範囲を教科書や理解本で復習しセミナーやリードαなどの問題集を並行しましょう。受験生になってから学習した範囲を一から学ぶ場合や浪人生は生物基礎も含め理解本で一通り学んでから問題集で演習することをおすすめします。
生物勉強法のポイント
道具を知るー基礎知識の習得
教科書の内容理解
教科書を一通り読み、その単元の大枠をつかむことが第一歩です。この段階では、用語の意味だけでなく、それらがどのように関連しているかを理解することが重要です。横のつながりを意識することと、それらについて表層の知識だけではなく概念を理解することで、思考問題を解く際の助けになります。
思考問題や記述問題の対策の前に、用語の定義をきちんと覚える
生物には多くの専門用語が存在するため、まずは教科書を通じて基本的な用語や概念を理解することが不可欠です。用語と定義を一対一で覚えるのではなく周辺知識とあわせて身につけていきましょう。
道具を正しく使いこなすー演習
問題集の活用
基礎知識が定着したら、問題集を使って演習に取り組みます。学校で使用している問題集の基本問題から始めて徐々に難易度を上げていくと良いでしょう。一周目で完璧を目指さないことが重要です。
実験考察問題への対策
大学入試では、知識だけでなく実験考察問題も出題されます。これらは単なる暗記ではなく、学んだ知識を基にして考える力が求められます。実験結果から何が分かるかを考察する練習も必要です。
思考問題への対処法
思考問題では、問題文に含まれる前提知識やヒントを整理し、論理的に解答を作成する力が求められます。そのため、生物の知識だけでなく、読解力や記述力も重要です。もし「何を書けばいいか分からない」という場合は、まず教科書の記述や模範解答を真似ることから始めましょう。専門用語や解答の組み立て方を学びながら、自然と解答の型が身につきます。こうした練習を繰り返すことで、思考問題への対応力が向上します。