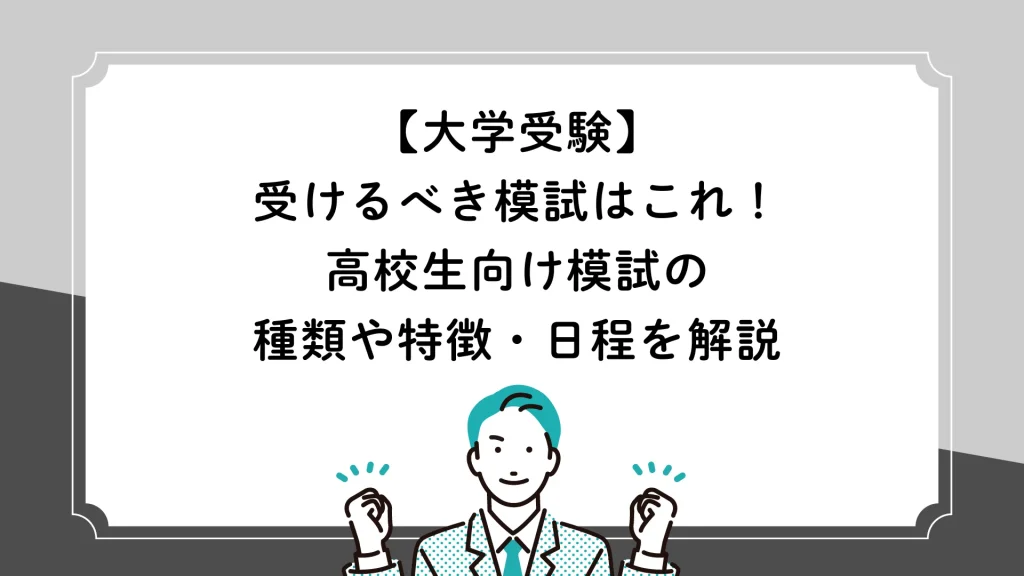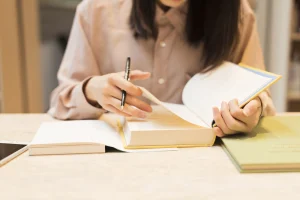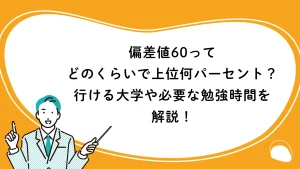「模試はそもそも何のために受けるんだろう」「いろんな模試があって、どれを受けたらいいかわからない」と思ったことはありませんか?模試を受けることで現在の実力を把握したり、志望校の合格可能性を探ったりなどが可能になりますが、数多く実施されているテストから、適切なものを選んで受験することが大切です。この記事では、模擬試験の種類や受けるべき理由、予備校別にお勧めの模試について紹介していきます。志望校や学力レベルに合ったテストを受験して、成績アップを実現させていきましょう。
高校生が模試を受けるべき理由
大学受験に向けて模試を受けることは大切だと言われていますが、その主な3つの理由について、以下で詳しく解説していきます。
現在の立ち位置を把握するため
模試を受けることで、現在どのくらいの実力があるのかを客観的に把握できます。高校の学内テストで出る順位は、学校のレベルによって変わるため、実力判定の精度としては高くありません。しかし、全国模試であれば地域内や学校内だけではなく、日本全体の中で自分がどのレベルに位置しているのかを知ることが可能になります。高3になると浪人生も同じ模試を受験するため、より正確な立ち位置が測定できるでしょう。また、模試を受けて今の立ち位置を確認することで、「次のテストまでには苦手単元を克服しておこう」「合格判定をDからCに上げるぞ」など具体的に今後の目標を立てられるので、モチベーションアップにつながりやすい効果もあります。
苦手分野を把握するため
模試を受験する理由として、苦手分野を把握することが挙げられます。模試の結果を受け取ると、つい点数や偏差値が気になってしまうものですが、自分の弱点や苦手単元を把握することが大切です。つまり、模試を受け終わったあとの復習がもっとも重要になります。間違えた問題はもちろん、あやふやなまま正解したものについても、しっかり解説を読み込み見直してください。ちなみに、受験者のほとんどが正解していない問題は奇問難問ですので、無理して手を出す必要はありません。模試の復習をキッカケにして苦手分野を把握、克服し、学力アップにつなげていきましょう。
志望校の合格可能性を見極めるため
模試を受けることで、志望校の合格可能性を見極めることができます。特に高校3年生と浪人生を対象として行われる東大模試や京大模試といった大学別模試は、受験者の母集団が本番に近いため、他の模試よりも合格判定の信頼性が高いと言われているテストです。そのため、もし大学別模試でE判定(合格可能性20%以下)が出た場合、秋以降であれば志望校の変更を検討したほうが良いと言われています。高校1、2年生のうちは模試の結果が悪かったとしても、それで志望大学を変える必要はありません。しかし高校3年生の場合は、合格できるかどうか判断する材料として、模試を有効活用していく必要があります。
模試はいつから何回受けるといい?
模試は年間を通して行われていますが、いつからどのくらいのペースで受けると良いのでしょうか?適切な回数は学年によっても異なるため、以下の解説をご覧ください。
高校1年生と2年生
高校1年生と2年生は季節ごと、つまり3か月に1回程度、模試を受験すると良いでしょう。はじめのうちは時間配分がうまくいかず最後まで解き終えられなかったり、あとから自宅で解き直したら問題なく正解できたりということもあるかもしれません。しかし、何度か模試を受けるうちに、会場の雰囲気にも慣れ時間配分も上手になっていきます。1、2年生のうちは、偏差値や合格判定などはあくまでも参考程度にとどめておきましょう。
これらをモチベーションアップに利用できるのであれば良いですが、あくまで大切なことは、苦手分野をあぶりだしてその後の学習で克服していくことです。詳しくは後述しますが、高校2年生はぜひ1月に行われる共通テストの同日模試を受験してみましょう。共通テストは高校2年生の学習範囲までで取り組むことができるため、理解度を確認するとともに、1年後の入試本番の雰囲気を味わえる貴重な機会だからです。
高校3年生
高校3年生は、月1回程度を目安として模試を受験していきましょう。旧帝大などの難関大学を目指す場合は、東大模試などの大学別模試を必ず受けてください。高校3年生は、今までとは異なり浪人生が模試に加わってくるため、特に夏頃までは実力の差を大きく感じる場合があります。そのため、偏差値が思ったように伸びず、場合によっては2年生までと比べて落ちてしまうこともあるかもしれません。
しかし、現役生は秋以降に成績がグンと伸びるケースが多くあります。偏差値にとらわれすぎずに、毎月の模試をペースメーカーとして利用していきましょう。合格判定については、夏まではあまり気にする必要はありません。偏差値や判定よりも、不正解だった問題や苦手分野を徹底的に克服していくように努めてください。
模試の種類
模試には大きく分けて3種類あり、志望する大学や学部によって受けるべきテストが変わってきます。以下で、それぞれの違いについて解説していきます。
マーク式模試
マーク式模試は、共通テストや一部の大学入学試験で使用されるマークシート方式のテストです。すべての問題が選択式で、一般的に問題数がとても多い傾向があります。そのため記述式模試などに比べスピード重視で、正確に早く問題を処理する能力が求められます。マーク式模試として有名なのは、1月に行われる大学入学共通テストに特化した「共通テスト模試」です。試験時間や出題傾向、配点なども共通テストに沿っているため、多数の生徒が受験します。
記述式模試
記述式模試は、国公立大学の二次試験や私立大学の個別試験に似た形式です。マーク式とは異なり、穴埋め問題や計算式を書かせる問題、論述問題などが出題されるため、スピードよりも思考力が求められます。また、一般的に処理能力を問われるマーク式よりも難易度が高いため、平均点が低めになる傾向があります。
大学別模試
大学別模試は冠模試とも呼ばれ、各大学の出題傾向に沿った問題が出題されます。そのため、その大学を志望する生徒のみが受験します。結果として母集団が限定され、より正確な自分の立ち位置が把握できるのが特徴です。大学別模試は東京大学や京都大学、大阪大学などの旧帝大や私立大学では早慶などの難関大学のみを対象として実施されます。受験回数が限られており、1回もしくは2回のみとなるケースがほとんどです。
高校生が受けるべきお勧め模試とは?
以下で、高校生が受験できる模試(2021年度)を一覧表で紹介します。また、河合塾・駿台・東進・ベネッセ・代々木ゼミナールを取り上げ、どの模試がどんな人におすすめなのかについて解説していきます。
高校生が受験できる模試一覧
・高校1、2年生を対象とした模試
| 高校1年生 | 高校2年生 | |
|---|---|---|
| 河合塾 | プライムステージ 1回(10月) 全統模試 4回(5、8、11、1月) | プライムステージ 1回(10月) 全統模試 3回(5、8、11月) 全統記述模試 1回(1月) 全統共通テスト模試 1回(1月) |
| 駿台 | 駿台全国模試 3回(6、10、2月) アドバンスト 1回(11月) | 駿台全国模試 3回(6、10、2月) アドバンスト 1回(11月) |
| 東進ハイスクール | 共通テスト本番レベル模試 4回(2、4、8、12月) 大学合格基礎力判定テスト 4回(5、8、12、3月) 共通テスト同日体験受験(1月) 全国統一高校生テスト 2回(6、11月) 高校レベル記述模試 2回(9、3月) | 共通テスト本番レベル模試 4回(2、4、8、12月) 大学合格基礎力判定テスト 4回(5、8、12、3月) 共通テスト同日体験受験(1月) 全国統一高校生テスト 2回(6、11月) 高校レベル記述模試 2回(9、3月) |
| ベネッセ | 総合学力テスト 3回(7、11、1月) | 総合学力テスト 3回(7、11、1月) 大学入学共通テスト早期対策模試(2月) |
| 代々木ゼミナール | 共通テスト模試 2回 大学別模試 1回 | 共通テスト模試 2回 大学別模試 1回 |
・高校3年生を対象とした模試
| 高校3年生 | |
|---|---|
| 河合塾 | プライムステージ 1回(4月) 全統共通テスト模試 3回(5、8、10月) 全統共通記述模試 3回(5、9、10月) 大学別模試 14回(7~11月) 全統プレ共通テスト 1回(11月) |
| 駿台 | 駿台全国模試 2回(5、9月) 駿台共通テスト模試 2回(5、7月) 駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試2回(9、10月) 駿台ベネッセ記述模試 1回(10月) 駿台プレ共通テスト 1回(12月) 大学別模試 13回(8~11月) |
| 東進ハイスクール | 共通テスト本番模試レベル 4回(2、4、8、12月) 大学合格基礎力判定テスト 4回(5、8、12、3月) 大学別模試 40回程度(5月~1月) 全国統一高校生テスト 2回(6、11月) 医学部82大学判定テスト(6、10月) |
| ベネッセ | 総合学力記述模試 2回(4、7月) 総合学力マーク模試 1回(6月) ベネッセ駿台マーク模試 2回(9、11月) ベネッセ駿台記述模試 1回(10月) |
| 代々木ゼミナール | 大学入学共通テスト入試プレ 2回(8、11月) 大学別模試 11回(6~11月) |
以下で、予備校別に模試の難易度やお勧めのテストを紹介していきます。
河合塾
河合塾の模試は難易度が標準的なこともあり、受験人数が多く、偏差値や合格判定の信頼度が高いと言われています。年1回のみ実施されるプライムステージという記述模試は、全統記述模試に比べると難易度は高めです。また、珍しいところでは、東京芸大、多摩美術大、武蔵野美術大、愛知芸大、京都市芸大向けの実技模試が実施されています。高校1、2年生向けには、自分の立ち位置を知り、苦手分野を知るために全統模試を受けることをお勧めします。
駿台
駿台予備校は、テストによって難易度が異なるのが特徴です。ベネッセとも共催して記述模試や共通テスト模試を実施していますが、駿台全国模試の方が難しいと言われています。高校1、2年生向けには駿台模試とアドバンストが実施されていますが、難関国公私立大や医学部を志望する人には、難易度が高い駿台模試をお勧めします。アドバンストはZ会と共催で行われていますが、駿台模試と比べると問題レベルはやさしめです。
東進
東進ハイスクールでは、試験実施から中5日で成績表が返却されるのが特徴です。模試を受けた記憶が残っているうちに結果を知ることができます。模試の種類も多く、高1、2対象の共通テスト対策のマーク式の模試や、高3生を対象とした医学部判定テストなどさまざまです。また、大学別模試では対象大学が他の予備校と比べると多く、受験回数も多い大学では4回もあります。大学別模試の対象大学は、名古屋大、東京大、京都大、九州大、東北大、大阪大、北海道大、一橋大、東工大、千葉大、神戸大、広島大、早稲田大、慶応大です。
ベネッセ
ベネッセが実施している模試は、一番難易度が低いと言われています。なかでも、総合学力テストは学校単位で受験するため、大学受験しない人も受ける模試です。そのため、偏差値はかなり高めに出る傾向があります。高い偏差値や合格判定が出ると嬉しいものですが、あくまでも参考程度にとどめておきましょう。逆に言えば、ベネッセの模試でミスした問題は確実に解けるように復習しておく必要があるととらえて、全問正解できるようにしておいてください。
代々木ゼミナール
代々木ゼミナールでは、模試の開催はほかの予備校と比べると少なめです。高校1、2年生向けに「全国共通テスト模試」、発展した内容を出題する「トップレベルチャレンジテスト」が実施されており、高校3年生向けには「大学入学共通テスト入試プレ」「大学別模試」が実施されています。大学別模試は、名古屋大、東京大、京都大、九州大、東北大、大阪大、北海道大、早稲田大、慶応大を対象として実施していますので、志望校があれば受験しておきましょう。
まとめ
この記事では、模試の種類や受けるべき理由、それぞれの予備校で実施している模試の特徴や日程についてお伝えしてきました。数多くの模試が年間を通して行われているため、学校や塾、予備校で強制的に受けさせられる模試とは別に自分で受ける場合は、実力アップにつながる模試を受験するようにしましょう。自分のレベルに見合わなかったり、志望大学とはまったく異なる傾向の模試を受けてしまったりすると、自信を喪失してしまう場合もあるので注意が必要です。上手に模試をペースメーカーとして利用し、志望大学の合格に向かって進んでいきましょう!