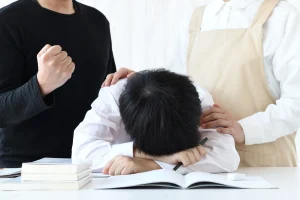大学受験をしようとするとき、その勉強の過程において、「模試」は非常に重要な意味を持ちます。ここでは、「そもそも模試は何のために受けるのか、模試の意味」「模試に向けて実践したい勉強方法」「模試を受けた後の勉強方法」について解説していきます。
まずは模試の意味を考えて! 「模試で良い点数を取ること」は目的ではない
模試(模擬試験。以下「模試」の表記に統一する)は、その名前の通り、「受験本番の試験を模して行われる試験」のことです。
いわゆる「学期末の試験」などとは異なり、その科目の内容すべてを出題に含むものであり、時間を計って、本番の受験形式と同じかたちで行われます。
模試は、学校を通して受ける模試(「学校模試」の名前で呼ばれることもある)もあれば、個人で申し込んで受ける模試もあります。
また、塾や予備校で行うこともあります。
また模試は基本的には全国レベルで自分の学力を測って志望校への合格可能性を探るものですが、超難関大学と呼ばれる大学に関しては「その大学を想定した模試」が個別に行われることもあります(京大模試など)。
学校のテストと模試の違い
学校で行われるテストと、模試はその性質が本質的に異なります。
【出題範囲】
学校のテストの場合、出題範囲が決まっています。
期末テストならばその学期に学んだ部分しか基本的には出ませんし、学年末のテストでも1年分の学習範囲が問われるだけです。
もちろんそこで点数を取るためには、それまでに積み重ねてきた土台(2年生の学期末テストならば1年生の、3年生の学期末テストならば1年生と2年生のときの)がなければなりませんが、その出題範囲はかなり限られているといえます。
対して模試の場合は、このような「出題範囲の決まり」がありません。
頻出問題や頻出カテゴリーはありますが、それでも、「この学期に習ったことだけが出る」「この年に習ったことだけが出る」ということはありません。
また現代文・古典や英語は、当然まったく知らない長文問題が出されることが基本となるため、いわゆる「丸暗記」だけでは解けない状況になる可能性が高いといえます。
【大学受験に使用できるかどうか】
学校のテストの成績は、大学受験でも直接的に使われることがあります。
特に大きな影響を及ぼすのが、学校推薦型選抜指定校の場合はこの傾向が顕著です。
この推薦形式は、高校―大学の信頼関係によって成り立っているため、「日頃からこつこつ勉学に打ち込んできたかどうか」が問われます。
ちなみに、学校からの推薦を受けたいと考える場合、「3年生の1年間だけ、定期テストで良い点数をとればよい」ということはなく、1年生のころから良い成績を維持しなければなりません。
模試の場合は、大学受験の合否に直接的な影響を及ぼすことはまったくありません。
模試でどれだけ点数が悪くてもそれを理由として不合格になることはありませんし、また逆に模試でA判定を取り続けていても本番の試験で失敗してしまえば不合格になることがあります。
極端な話をいえば、模試をまったく受けずに受験に臨むこともできます。
ただ模試を受けることで、自分のレベルや弱みを客観的に知ることができ、受験突破のための対策も練りやすくなります。
模試はそれ自体が大学受験の結果と直結することはなくても、大学受験を突破するために受けるべきものだといえます。
【大学受験本番のときとの共通点の有無】
学校の定期テストは、自分が毎日過ごしている学校内で受けることになります。
受ける仲間も自分と同じ学校の人であり、監督も先生が務めます。
そのため、大学受験本番のときのテストとは、まったく異なった「慣れ親しんだ環境での試験」となります。
しかし模試の場合は違います。
学校模試もないわけではありませんが、多くの場合、「まったく知らない人たちと、まったく知らない会場で、まったく知らない先生が監督を務める」という状況で受けることになります。
これは本番の受験のときとほぼ同じ状況です。
そのため、「本番はいつも緊張してしまう」「自分のレベルも知りたいが、本番の雰囲気にも慣れたい」という人にとって、模試を受けることは非常に良い経験となるでしょう。
| 範囲 | 大学受験との直接的な関わり | 本番の雰囲気との共通点 | |
|---|---|---|---|
| 学校での定期テスト | 狭い 予想が非常につきやすい | ある、特に推薦の場合は非常に比重が大きい | ほぼない |
| 模試 | 広い 予想がつきにくい | なし | ある |
模試は何のためにある?
上記を踏まえたうえで、「模試は何のためにあるのか」を考えていきましょう。
模試を受ける前にまず確認しておきたいのは、「模試で良い点数をとることのみ」を学習の目的にしてはならない、というものです。
上でも述べたように、模試は大学受験の点数や評価とは直結しません。
模試でも高い点数をとれるように日々しっかり勉強することは大切はありますが、模試の結果に一喜一憂したり、模試で良い点数をマークするためだけに勉強をしたりするのではなく、「模試をベンチマークにする」「模試で自分のレベルを測る」といった視点を持つことが大切です。
模試を受けることのメリットとは
ここからは、模試を受けることのメリットについてより深く紹介していきます。
場に慣れることができる
上でも述べたように、模試は学校での定期テストとは異なり、受験本番さながらの雰囲気のなかで受けることができるものです。
知らないライバルたちに囲まれて、普段勉強している教室とは異なる場所で、試験監督に見られながら試験を受けることができます。
これは初めは非常に緊張するものですが、このような環境に慣れておけば、「本番で緊張しすぎて力が発揮できない」という状況になる危険性を低くすることができます。
「テストに限らず、学芸会などでも本番だと緊張することが多かった」という人は、特に積極的に模試を受けるべきでしょう。
総合的な学習の理解度を知ることができる
頻出問題・頻出カテゴリーはあるものの、模試は定期テストよりも出題範囲を予想することが難しく、丸暗記のみに頼った学習や、「多分こうだろう」という程度の理解度ではでは太刀打ちできないことがよくあります。
その科目の基礎や理解度そのものを問うたうえで、さらに応用を求めてくる問題が多いため、単元一つひとつをしっかり理解しておかないと解くことができません。
逆にいえば、模試を受けることで、「定期テストでは点数が取れていたが、総合的な理解ができていなかった」「土台をおろそかにしてしまっていた」ということが自覚できるようになります。
そしてこの「自覚」は、模試の後の勉強を行うときに非常に役に立ちます。
自分の偏差値などを知るために役立つ
模試では、全国レベルで自分の偏差値を知ることができますし、志望校の合格可能性評価を客観的に知ることができます。
志望校の合格判定評価は
- A(合格可能性80パーセント以上)
- B(同65パーセント)
- C(同50パーセント)
- D(同35パーセント)
- E(同20パーセント以下)
のように表示されます。
もちろん、模試を受けた後でも勉強は続いていくため、ここでA判定が出たからといって「必ず合格できる」というものではありません。
ただ、模試で志望校の合格可能性評価や客観的な自分のレベルを知ることで、「A判定が出ているから、この学校は滑り止めとして、もう1個レベルの高い学校を受けよう」「C判定ではあったが、どうしてもこの学校に行きたいから今からもっと勉強しよう」「E判定だったので、ほかの学校を視野に入れよう」などのように、「模試後の選択肢」を考えやすくなります。
苦手な分野が分かる
模試を受けるもっとも大きなメリットのうちのひとつとして、「苦手な分野が分かる」というものがあります。
模試は単純に点数だけを出すものではありません。
自己採点と合わせることで、「どこで間違えたか」「どの単元が弱かったか」「正解はしたけれど、迷ったところはどこだったか」を洗い出すことができます。
これによって、自分の苦手な分野を把握することができるのです。
特殊な受験方法(面接+履歴書+小論文のみなど)でもない限り、大学受験では、総合力が求められます。
「5教科以上必要な大学を受ける」という場合は当然5教科すべての点数がある程度高いことが求められますし、「英語のみ」としているところではリーディング能力もリスリング能力もライティング能力も求められます。
つまり、「穴」「苦手」「弱み」があると、不合格になる確率が高くなります。
模試で苦手な分野を客観的に把握できれば、その「穴」「苦手」「弱み」を集中的に学習し、合格に近づけるようになります。
「目標」を作ることで勉強に意欲的になれる
上では、「模試で良い点数をとることだけを目的として勉強を行うことは推奨されない」としました。
しかし「模試」というひとつの明確な予定を入れることで、「そこまでの間に、〇〇の部分まで勉強をすませよう」「模試があるから、頻出問題を調べて対策をしていこう」などのようなモチベーションを保ちやすくなることはたしかです。
そのような意味においては、「模試をひとつの目安として、そこに向けて勉強していくこと」は無駄にはなりません。
模試に向けてやっておきたい勉強方法、4つの点から解説
ここからは、本番の試験と同じような環境・似た出題方法が選ばれる「模試」に向けた勉強方法を紹介していきます。
ポイントとなるのは、以下の4点です。
- 過去問をしっかり解く
- 単元を総まとめ的・網羅的に勉強していく
- 時間を実際に計測して問題を解いてみる
- 暗記は基本的には前日でOK
一つずつ紹介していきます。
過去問をしっかり解く
試験では、「過去の問題とそっくり同じもの」が出る確率は非常に少ないといえます。
ただ過去問をしっかり解いていくことで、出されやすい単元や傾向、問題形式を予想することができます。
一般的に、大学受験における過去問は2~5年分程度を目安に解いてみるのが望ましいとされています。
5年分ほどの過去問を解けば、「どのような問題が出されやすいか」を知れるだけではなく、「問題に取り組むこと自体」にも慣れていくことができます。
過去問を解くときには、惰性で解くのではなく、毎回その出題の意味や、解いていくための手順も確認することが重要です。たとえば答えが「5」であるとすると、単純に「5」という数字を出すのではなく、「この問題はこの公式を当てはめて、このように解いていくことで、5という解答が導き出せる」のように、「解答にたどり着くルート」「解答の根拠」を示せるようになることが重要です。
単元を総まとめ的・網羅的に勉強していく
繰り返しになりますが、模試や本番は定期テストとは異なり、科目・単元の総まとめ的な問題が出されます。
一つひとつの単元に対してしっかり勉強することはもちろん、広い分野の知識をつけていくことが求められます。
もちろん、人によって「得意な分野」はあります。分かりやすい例で言えば、「子どもの頃学習まんがで読んできたので、平安時代から江戸時代までの歴史にはとても詳しい」というケースです。
ただ受験においては、どれだけ得意な分野であっても、それだけでテストが構成されることはありません。
そのため、得意な部分以外の勉強も総まとめ的に勉強していくことが非常に大切です。
時間を実際に計測して問題を解いてみる
模試や本番の試験を受けるうえで、盲点となりやすいのが「時間」です。
日頃の勉強においては、「一つの問題をじっくり解く」「解答に至るまでのルートを探すことが重要なので、その根拠となる部分を教科書・参考書のなかから見つけて復習していく」という工程が非常に大切です。
このような勉強は、学力をつけるうえでの土台となるからです。
しかし模試や本番の試験には、「時間制限」があります。
時間が来てしまうと、当然試験はそこで終わりです。
答えを導き出せる実力はあっても、時間が足りなくなってしまえば空欄で出すことになってしまいます。
このような事態を避けるために、模試が近くなってきたら、時間を実際に計測して「問題を解くのにどれくらいの時間がかかっているか」を確認しましょう。
また模試や本番の試験では、自己採点のためのメモを作ることも必要になってきます。
そのため、時間の計測を行う場合は、問題を解く時間+自己採点を行うためのチェックをする時間でみる必要があります。
暗記は基本的には前日でOK
数学や国語などは暗記だけでは解けない問題もあります。
しかし英語の場合は英単語を覚えていることが長文読解のキーとなりますし、日本史や世界史などは特に暗記が重要な意味を持ってくるものです。
この暗記に関しては「最後の仕上げ」「模試の前日の見直し」を行うことが効果的だとされています。
ただもちろんこれは「今までも何度も読んできたこと」「今まできちんと勉強してきたこと」が前提となる話ではあります。そのうえで、「しっかり勉強をしたうえで、最後の対策として暗記や見直しを行うこと」が大切になるといえるでしょう。
これが一番大事! 模試を受けた後の勉強方法
先述したように、模試はそこで高得点を取ることだけを目的とするものではありません。
模試の点数が悪かったからといって落ち込む必要はなく、次につなげることが大切です。
模試は、むしろ、その結果を確認することでその後の勉強方法を知るためにあるものだといえるでしょう。
模試の結果を受けた後の勉強方法として大切になるのは、以下の4点です。
- 「失敗の分析」を行う
- 点数が悪かったところを重点的に学習する
- 「過去にも出ていたはずなのに、今回解けなかったところ」を振り返る
- 学習スケジュールの見直しを行う
- 【補足】まだ早い時期なら「この科目は必要か」も考えてみる
一つずつ紹介していきます。
「失敗の分析」を行う
まず、解けなかった部分の分析を行いましょう。
問題を解けなかったことには、必ず理由があります。
①マークミスや計算ミス
②一度勉強していたところのはずだが、過去問とは違う出され方をしていたため解けなかった
③まったく手も足も出ず、解答ができなかった
それぞれの意味と、その後の勉強方法を考えていきましょう。
①の場合は、本来ならば得点とできたところの点数を落としているわけですから、本番の受験では大きなマイナスとなります。ただ、しっかり理解ができていたうえでのミスであれば、「確認をすること」「落ち着いて試験を受けること(場慣れすること)」で、確実な得点につなげていけるということです。
②に関しては、「分かったつもりになっていたが、問題に対する理解度が浅かったことによる不正解」だといえます。
この場合は、もう一度「正答を導くための過程をきちんと理解できているか」を確認しましょう。
インプットは十分にできているということなので、それをきちんとアウトプットする術を身に着けられれば、すぐに得点アップにつなげられます。
③のケースでは、根本的な見直しが必要です。
もう一度教科書を読み直すことから始めましょう。
また、分からないところがあれば、学校の先生や塾の講師に積極的に質問することが大切です。
「なぜ得点につなげられなかったか」を知ることは、「どのようにしたら得点につなげられるか」の可能性を探るためのステップともなります。
点数が悪かったところを重点的に学習する
模試で点数が悪かったところを重点的に学習することは、受験を勝ち抜くうえで非常に大切です。
たとえば数学Bの場合、単元としてベクトルがあり、数列があり、統計・確率分布があります。
どれを得意とするか、また不得意とするかは人によって違いがあり、なかには「ベクトルは90パーセント取れていたが、数列は正答率が20パーセント程度だった」という人もいます。
当然のことですが、人間は「自分ができるところは、楽しい」となりがちであるため、このような場合はついついベクトルの勉強をしたくなってしまいがちです。しかし受験を突破するうえで重点的に勉強するべきは、まだ80パーセントの伸びしろがある数列の方です。
模試の結果で点数が悪かったところをしっかり勉強して、穴をなくすことが大切です。
なお勉強には「ためになる息抜き」も必要なので、数列の勉強に飽きたらベクトルの高難易度の問題を休憩がてら解いてみる、というのは面白い方法です。
「過去にも出ていたはずなのに、今回解けなかったところ」を振り返る
「過去問でやっていた気がするが、あまり重要度が高くないと勝手に判断して飛ばしてしまった単元・問題が、模試で出題された……」ということは、模試において往々にしてあり得ることです。
このような場合は、その単元・問題が受験時において重要な意味を持つということですから、その部分の復習をしっかり行いましょう。また、「なぜ解けなかったのか」「どこまでなら解けたのか」を見直し、「解けなかったところからの復習」をしていくと、学習時間の節約になります。
学習スケジュールの見直しを行う
模試を受けることで、「今自分の学習がどこまで進んでいるか」「志望校を突破するためには、どれくらいの勉強時間が必要か」が分かるようになります。塾の講師などと相談をして、必要な勉強時間や学習スケジュールの組み直しを行いましょう。
なおこのときには、「予備日」をとっておくとよいでしょう。
学習計画は、どれだけ綿密に練り上げても、100パーセントスケジュール通りに進むことはありません。
息抜きの時間も必要ですし、体調を崩して休養が必要になることもありますし、習熟に想像以上の時間がかかることもあります。
そのため、「1週間に1日、空白の時間をとっておく」などのようにしておくと安心です。
【補足】まだ早い時期なら「この科目は必要か」も考えてみる
補足的な話ではありますが、模試の結果が著しく悪い科目がある場合、「本当にその科目は必要か?」という根源的な問いかけを自分自身にしてみるのもひとつの手です。
たとえば、今高校2年生の国公立志望の文系コースで、数学2Bの成績がずっと悪いかつ数学2Bを選ばずに済む学校にも魅力的な学科があるという場合などです。
「模試で極端に成績が悪く、その科目に興味もない(あるいはむしろ苦手意識がある)。
その科目があれば選択肢は広まるものの、使わなくても済む大学でも魅力的なところがある」という場合、模試の結果を判断材料として、切り捨てるのもひとつの戦略です。
模試は、自分の学力を知るためのベンチマーク
「その学期で習った分野が出る」という定期テストとは異なり、模試は総まとめ的な内容が出題されます。
模試の結果は受験の合否と直結はしませんが、模試を受けることでモチベーションアップが期待できたり、自分の苦手な分野を洗い出せたり、自分の学力レベルを客観的に知ることができたりといったメリットが得られます。
また、模試の結果を見て、より良い勉強方法を探っていくこともできます。
模試は、受験勉強においてベンチマークとなり得るものです。
模試の点数が悪かったからといって落ち込みすぎる必要はありません。
「模試によって苦手な部分を見つけ出せたとポジティブにとらえることが、合格にいたるために重要なことだといえるでしょう。
アクシブアカデミーでは、模試の自己採点の確認を行い、より良い学習計画作りのサポートをしています▶アクシブアカデミーの無料受験相談はこちらから!