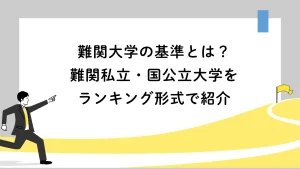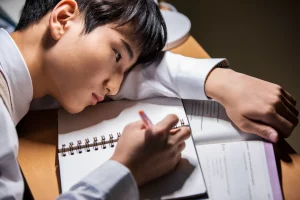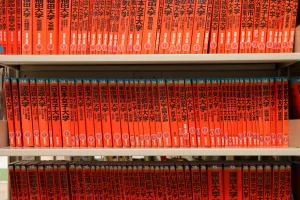受験は自分との戦いである一方で、自分の現在地を知るためには比較対象が必要です。
模試の結果はもちろん、勉強時間も参考になるため、一般的なデータと比較して自分の勉強時間が適切なのかを知りたい方は多いでしょう。
今回は受験生の勉強時間や難関大学の合格に必要な時間を解説します。
あわせて、勉強を効果的にする方法や勉強時間を捻出する方法も紹介します。
高校1・2年生の勉強時間は1~3時間
受験に向けた勉強時間というと、高校3年生の勉強時間が気になりますが、高校1・2年生の勉強時間も把握しておくとよいでしょう。
高校1・2年生の段階は基礎固めの段階であり、基礎固めにどれだけ時間を割いているかが参考になるためです。
弊社が調査したところによると、高校1・2年生の勉強時間は平均1〜3時間です。
高校1・2年生は部活や課外活動も多く、受験からは遠いため、少ない勉強時間となっています。
本章では高校1〜2年生の平均勉強時間を解説します。
高校1年生の勉強時間は平均1~2時間
高校1年生の勉強時間の平均は、平日1時間・休日2時間です。
受験に最も遠いこともあり、モチベーションが高くないことから、少ない勉強時間となっています。
また部活動や課外活動に力が入る学年であることも、少ない勉強時間につながっています。
高校1年生の段階で、基礎的な内容を抑えることが受験での飛躍につながるため、わずかな時間でも机に向かうとよいでしょう。
高校2年生の勉強時間は平均1~2時間
高校2年生の勉強時間の平均は、平日1時間・休日2時間です。
部活動や課外活動が続いていることから、勉強に集中するのが難しい学年となっており、勉強時間を確保できない学生も少なくありません。
一方で次の年は自身が受験を迎えることから、徐々に勉強時間を増やしている方もいます。
受験に備えて塾や予備校を検討している場合は、2年生の夏までに決めておくと、スムーズに受験へ臨む体制が作れます。
大学受験を迎える高校3年生・受験生の勉強時間は3~10時間
受験を迎える高校3年生がどれくらいの勉強時間なのか、同じ受験生はもちろん、高校1・2年生の方も気になるところでしょう。
弊社が調査したところによると、高校3年生の勉強時間は1日3〜10時間です。
受験を控えることもあり、高校3年生の勉強時間は非常に多くなっています。
本章では、受験を迎える高校3年生の勉強時間と難関大学や国公立大学に必要な勉強時間を解説します。
平日の受験生の勉強時間は3時間前後
高校3年生の平日の勉強時間は、平均3時間です。
平日は学校があることから、勉強時間が帰宅後から就寝するまでの間に限られるため、3時間前後となっています。
帰宅後に勉強時間の確保が難しい場合は、早起きをして通学前に勉強をすることをおすすめします。
休日の受験生の勉強時間は5時間前後
高校3年生の休日の勉強時間は、平均5時間です。
休日は学校がないことから、勉強時間が確保できるため、勉強時間が増加しています。
睡眠時間を除くと、16〜17時間前後があり、残りの時間をいかにして勉強時間にできるかが休日の勉強時間を伸ばすカギといえるでしょう。
夏休み・冬休みの受験生の勉強時間は10時間
高校3年生の長期休暇の勉強時間は、平均10時間です。
長期休暇は休日よりさらに時間が確保しやすく、受験生としての意識が高まっているため、勉強時間が増えています。
長期休暇の場合は休日と異なり、同じリズムが長期間続くことになります。
午前中や午後、夜間で取り組み内容を変えるなど、効率的に勉強できるようにスケジュール管理を工夫しましょう。
難関大学の合格に必要な勉強時間はおよそ3,500時間
勉強時間が必ずしも結果につながるわけではありませんが、一つの目安となります。
東京大学や京都大学など難関大学の合格に必要な勉強時間は、およそ3,500時間といわれています。
3,500時間は、高校3年生の1年間では到達が厳しい数値であり、1〜2年生の間にコツコツと勉強しなければ届かない数値です。
国公立大学の合格に必要な勉強時間はおよそ3,000時間
国公立大学の合格に必要な勉強時間は、およそ3,000時間といわれています。
難関大学より必要な勉強時間は減っている一方で、決して少なくない数値です。
国公立大学の勉強時間が増える要因としては、5教科7科目を課されるなど対策範囲が広いため、必要な勉強時間も比例して多くなります。
私立大学の合格に必要な勉強時間はおよそ2,500時間
私立大学の合格に必要な勉強時間は、およそ2,500時間といわれています。
決して少ない数値ではありませんが、国公立大学より勉強時間が少ないのは科目数が要因です。
私立大学の場合は受験に必要な科目数が減ることから、勉強時間が抑えられる傾向にあります。
受験生の勉強時間をより効果的にするポイント
受験生は長時間勉強することになりますが、できればより効果的な時間にしたいと誰もが思うでしょう。
本章では、受験生の勉強をより効果的にするポイントを解説します。
パフォーマンスの高い朝の時間を有効活用する
受験勉強では、難易度の高い問題や複雑な問題、苦手な内容など集中して取り組みたい科目・内容があるでしょう。
集中が必要な科目・内容がある場合には、午前中に取り組むことをおすすめします。
一般的に人間の脳は、起床後から午前中が最もパフォーマンスが高い状態とされているためです。
連休や長期休暇になると、午前中は睡眠時間に当てがちですが、人間の生理的な作用を利用しない手はありません。
パフォーマンスの高い時間帯を逃さないように、午前中から勉強に取り組みましょう。
勉強に集中できる空間で取り組む
長時間の勉強をより集中できる場所で取り組めば、さらに高い効果が期待できます。
学校の図書館や予備校の自習スペースなど一目がある場所で取り組むと、勉強モードに入りやすくなります。
自宅の場合、周囲に勉強の妨げとなる物があり、また一目がないことから勉強がおろそかになるケースは少なくありません。
特に勉強時間が長くなるほど、集中力が低下するため、自宅では集中しにくくなります。
移動時間は惜しいですが、勉強の場所を変えることは気分転換にもなるため、おすすめです。
周囲から刺激でモチベーションを上げる
勉強に対するやる気が上がった状態の方が、効率的に取り組めるのはいうまでもありません。
モチベーションを上げる方法は個人で異なりますが、受験シーズンであれば、同級生や先生と話して刺激をもらう方法がおすすめです。
同じ大学を狙う受験生が頑張っている話を聞けば、自分も頑張ろうと思えるため、自然とモチベーションアップにつながります。
また受験に多くの不安を抱えると思いますが、先生に相談することで自信を持って受験に打ち込めるようになります。
運動の習慣も入れる
勉強の効率を上げるには、脳のパフォーマンスを向上させることも一つの方法です。
脳のパフォーマンスを向上させる方法はいくつかある中で、有酸素運動はおすすめの方法です。
2017年に筑波大学が発表したデータによると、短時間の運動でも人間の記憶力が高まることが判明しています。
長時間の運動は勉強時間の減少につながるため、できれば避けたい方は少なくありません。
一方で短時間の運動であれば、時間の融通が利きやすいことから、パフォーマンスを上げるおすすめの方法といえるでしょう。
散歩やランニングは息抜きになることから、勉強に向かう活力になるため、おすすめです。
受験生が勉強時間を捻出する4つの方法
1日は長いように見えて、あっという間に終わるため、勉強時間が思うように作れないと悩む受験生は多いでしょう。
本章では受験生が勉強時間を捻出する方法を解説します。
1日のスケジュールを見直す
勉強時間が見つけられない方におすすめなのは、スケジュールを可視化してみることです。
スケジュールの可視化を通して、1日の時間の使い方を改めて見直せば、勉強時間を捻出することが可能です。
1日のスケジュールを円グラフなどで可視化してみるとさまざまな発見があり、意外と不要な時間が見つかります。
たとえば、少し長い休憩時間や身支度に時間がかかりすぎているなど、切り詰められる時間がいくつか浮かび上がります。
勉強のパフォーマンスや日常生活に支障のない範囲で、改めて1日のスケジュールを見直してみましょう。
移動時間や休み時間など隙間時間にも勉強する
「塵も積もれば山となる」との言葉があるとおり、僅かな時間でも勉強をすれば、勉強時間が増やせます。
移動時間や休み時間など隙間時間が勉強時間になると認識している方は多くありません。
ですが、隙間時間でも勉強を重ねると、トータルでは大きな時間になります。
たとえば、隙間時間を生かして毎日10分でも勉強をすれば、1週間で70分も勉強したことになります。
1回では僅かな時間でも、積み重ねると大きな差を生むため、隙間時間での勉強はおすすめです。
スマートフォンの使い方を見直す
勉強時間が思うように捻出できないのは、時間泥棒がいるからかもしれません。
現代社会において、最も時間泥棒になりがちなのはスマートフォンの利用です。
軽い息抜きのつもりが長時間の利用となっているケースも少なくないため、使い方を一度見直してみましょう。
昨今のスマートフォンは利用時間を表示してくれる機能・アプリもあります。
ポモドーロ・テクニックを使う
受験生の中には長時間の集中を得意としないことから、勉強時間が思うように増やせない方もいるでしょう。
集中力が続きにくい方におすすめなのは、ポモドーロ・テクニックの活用です。
ポモドーロ・テクニックとは、25分間の集中と5分間の休憩を繰り返すことで、集中力を維持しながら作業に取り組むタイムマネジメントの手法です。
ポモドーロ・テクニックのポイントは短い休憩を挟むことで、疲労を回復させることができる点です。
短いスパンではありますが、繰り返しをおこなうことで勉強時間の増加につなげることができます。
受験生が勉強時間の不足を感じた際の注意点
世間一般の受験生や知人の勉強時間と比べて、自分の勉強時間が少ない場合、焦りを感じる方もいるのでしょう。
モチベーションが上がる分には問題ありませんが、勉強時間の少なさから無謀なスケジュールで勉強時間を増やそうとする場合には注意が必要です。
本章では受験生が勉強時間の不足を感じた際の注意点を解説します。
長時間の勉強=合格とは限らない
志望校への合格には、長時間の勉強が必要と考える方は少なくありません。
志望校に合格した人は長時間の勉強を重ねたかもしれませんが、長時間の勉強が必ず結果につながるとは限らないため、注意が必要です。
学力の向上には勉強時間の他に、効果的に勉強できるかも関係しています。
周囲と比べて勉強時間が少ない場合でも、現時点で結果が伴っているなら問題はないといえるでしょう。
周囲と比較して、勉強時間が少ない場合でも極端に焦りを感じる必要はありません。
睡眠時間を削るとパフォーマンスは低下する
勉強時間を確保しようと思った場合、多くの方は真っ先に睡眠時間を削って勉強時間に充てようとします。
1日のスケジュールをみると、睡眠時間が占める割合は非常に多いため、睡眠時間を削りたくなります。
ですが、睡眠時間を削ると脳のパフォーマンスが低下するため、受験生には特におすすめできません。
首都大学の研究結果によると、短時間の睡眠では記憶力と思考力の低下が見られることが判明しています。
記憶力と思考力は受験生にとって武器であり、低下は自身の首を絞めることになります
勉強時間を確保したい場合は、1日のスケジュールの見直しから始めるとよいでしょう
参考:首都大学東京 睡眠時間が翌日終日の認知・運動機能に与える影響
まとめ
今回は大学受験を迎える受験生の勉強時間と効率を高める方法を解説しました。
今回解説した内容をまとめると以下のとおりです。
- 受験生の勉強時間は平日3時間前後、休日で5時間前後
- 勉強の効率を上げるためには時間や場所に気を使う
- 勉強時間を捻出するには1日のスケジュールを見直す
勉強時間の長さが結果に直結するわけではありませんが、勉強時間は自分と周囲を比較する際の一つのバロメーターになります。
受験を迎える方はぜひ本記事で紹介した勉強時間を参考にしつつ、自身のペースで取り組んでいただければと思います。