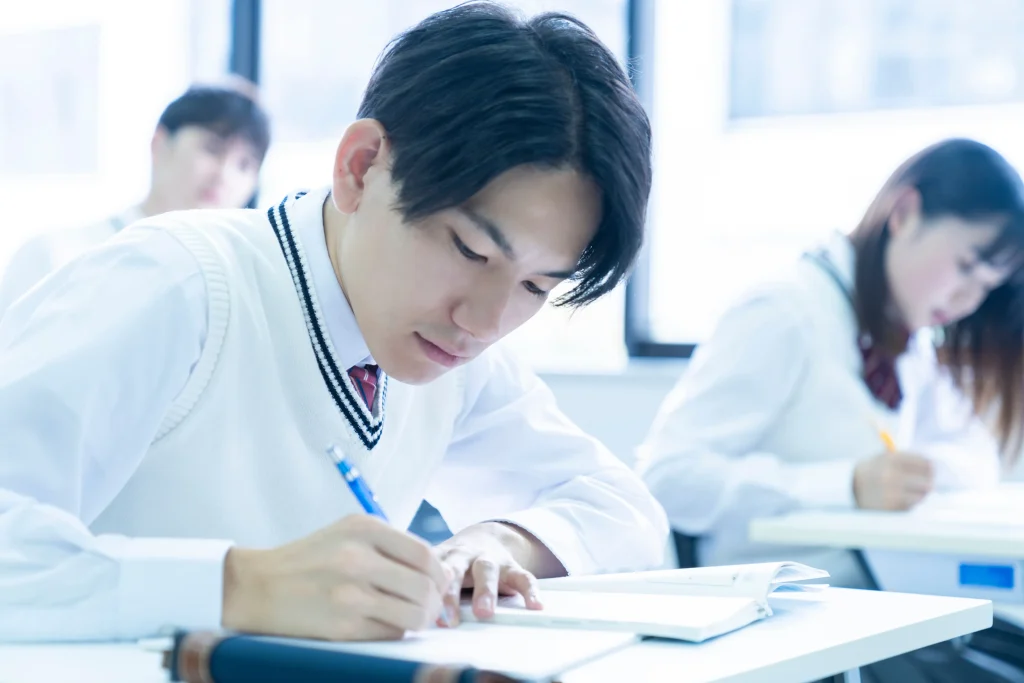誰しも一度は「やらなきゃいけないとわかっているのに受験勉強に集中できない」「受験勉強をしていても集中力が持続しない」と悩んだ経験があるのではないでしょうか。
大学受験はその後の人生を左右する大きな分岐点。
絶対に合格を手に入れるためにも、勉強に集中できない原因を探り、集中力を高める方法を取り入れましょう。
今回の記事では勉強に集中する方法7選をお伝えしたいと思います!
勉強に集中する方法7選とは?
ズバリ、
- 集中できない原因を知る
- 勉強できる環境を整える
- 勉強する場所を変える
- スケジュール管理を見直す
- モチベーションを高める
- 体調管理を徹底する
- シングルタスクを意識する
です!
順番に一つひとつ見ていきましょう。
集中できない原因を知る
集中できない原因には
- 外的要因(環境)
- 内的要因(スケジュール管理・モチベーション・メンタルヘルス・マルチタスク)
があります。
環境の影響
「よし!やるぞ!」と自分の部屋にこもって勉強を始めても、ふと顔を上げると目に入る本棚に並んだお気に入りの漫画や雑誌。
「ダメダメ!」と視線を教科書に戻しても、今度は耳から入ってくる友達からのラインやDMの通知音。
勉強への集中力を阻害する誘惑がたくさんある自分の部屋から、「勉強しなくちゃ」とリビングに移りますが、今度は「家族が見ているテレビの音や会話が気になって集中出来ない」という経験をした人も多いのではないでしょうか。
視覚からの刺激や周囲の音は勉強に集中出来ない原因の1つと言えます。
また、部屋が寒い・暑い、机や椅子の高さが合わない、シャーペンが太すぎ(細過ぎ)て手が痛くなる、など、一見「そんなことで?」と思ってしまうことも、集中力が途切れてしまう一因となり得ます。
スケジュール管理の問題
優先順位をつけるのが苦手な人、スケジュールを把握できていない人もまた、集中力を持続させることが難しそうです。
まず何をやるべきかがわからなかったり、勉強をどう進めるかというスケジュール自体が曖昧だと、肝心の勉強に向けるべき集中力が分散されてしまいます。
勉強に対するモチベーション不足
受験勉強を進めるにあたり、目的や目標が不明確だとやる気がわかず集中力が持続しません。
例えば、具体的な進学先や進路が決まっていない場合、自分で感じている以上にメンタル面が不安定となり、勉強していてもそのことばかりが気になってしまったり、逆にぼーっとしてしまう、ということがあるかも知れません。
メンタルヘルスに問題がある
受験のプレッシャーや模試の結果がふるわないことへの焦りは、ストレスや不安となり勉強への集中を妨げる原因となります。
また、体調不良で食事がとれていなかったり睡眠不足でぼんやりしてしまうなど万全のコンディションでない場合も、集中力が阻害されてしまいます。
マルチタスクの弊害
勉強をしながらAirPodsで音楽を聞いたり、スマホで動画を流すという人は多いですが、気付くとノートを書く手が止まり音楽や動画に夢中になっていた、という経験はありませんか?
同時に複数のことをこなすことをマルチタスクと言います。
従来、マルチタスクは時間を有効に使うことができ、非常に効率的だと言われてきましたが、実は近年「効率的であるかは懐疑的である」という声が上がっているのです。
「マルチタスクが可能であるというのは幻想です。1 つの作業からもう 1 つの作業へとす
ばやく切り替えることを繰り返しているだけであり、切り替えのたびに時間とエネル
ギーが余分に失われます。そのため、1 つの作業に集中するほうが、ほぼどんな場合で
も確実に効率的なのです。1 つの作業に集中し、それが終わってから次へ移ることで、
無駄な切り替えコストを払わずに済みます。」
(SAHAR YOUSEF 博士、カリフォルニア大学バークレー校、認知神経科学者)
つまり、マルチタスクとは「脳が複数のタスクを同時に処理している」のではなく、「脳が時間とエネルギーを使い、迅速に切り替えを行っている」に過ぎないのです。
タスクを切り替えるたびに時間とエネルギーを消耗し、集中力が分散し、途切れてしまうと言えます。
一見、音楽を聴きながら効率的に勉強しているように見え、実は脳は「音楽を聞くこと」と「勉強すること」の切り替えを絶え間なく行っている…….
想像しただけでどっと疲れてしまいます。
このように、勉強に集中できない原因は一つではなく、また人それぞれ違います。まず、最初に自分の集中できない原因は何かを知ることが、対処法を見つける手がかりとなります。
勉強できる環境を整える
視覚情報を調整(加減)する
ノートや黒板の文字を見る、教科書や参考書を読むなど、勉強をする時には常に目を使っています。
実際、脳に伝わる情報の約8割が視覚情報であることがわかっており、何かを「見る」ということは、常に脳に負荷がかかっている状態なのです。
そんな状態で、「さあ休憩だ!」とスマートフォンやテレビを見ることは、果たして脳を休めることになるのでしょうか?
答えは明確、NOです。
そして、脳疲労の原因の一つであるブルーライト。
スマートフォンやパソコン、ゲーム機器などのデジタル機器の画面から発光するあの青色光です。
夜間や寝る前にブルーライトを浴びると、本来なら夜間睡眠中に分泌されるメラトニン(別名:睡眠ホルモン)の分泌が抑制されてしまうことがわかっています。
そうすると、脳は夜なのに「今は昼間だ」と誤認識してしまい、なかなか寝付けず、やっと眠りについたと思えばすぐに起床時間です。
睡眠不足になるのはもちろん、睡眠の質も低下します。その結果、日中ぼーっとしてしまい、集中力が欠如するのです。
まずは
- 漫画や雑誌、テレビなどが目に入らないように、机の配置やものを置く場所を配慮する
- 休憩時間はスマートフォン、パソコン、テレビなどの電子機器は使わない
など、視覚情報を調整(加減)することが大切です。
そして、45分勉強したら5〜10分の休憩を挟むというサイクルで取り組んでみましょう。
また、英単語や公式などの暗記ものは「15分+5分休憩を2サイクルで行う」という分散型学習の方が記憶に残りやすいと言われています。
さらにこの方法で暗記学習を行うのは、夜寝る前がベストタイミング!
なぜかというと、「睡眠中はその日覚えたものが無意識下で定着する」と科学的に証明済みなのです。
参考URL:「睡眠不足とブルーライト」独立行政法人 筑後市立病院
参考URL:「暗記は夜寝る前」は、もはや当たり前。その後の行動が記憶の定着を左右する!』ダイヤモンドonline
遮断したり排除したりすることをいくつか提案しましたが、ここで一つ追加する案を!
「緑視率(りょくしりつ)」という言葉をご存じでしょうか?
耳慣れない言葉ですが、「緑視率」とは人の目に見える緑の割合を表しています。
緑視率が高くなるということは、視界に入る緑の量が増えることを意味し、様々なメリットがあることがわかっています。
その中の一つが「ストレスの軽減による集中力の向上」。
さらに具体的にいうと、「緑視率が10〜15%の時に人の集中のパフォーマンスが最も高まる」という、多くの研究結果が報告されています。
スッキリ整った机の上に観葉植物を一鉢置くことで、リラックスでき、集中して勉強に取り組める快適な空間になりそうです。
勉強する場所を変える
図書館や自習室、公共スペースなどを利用する
受験生にとって家はリラックスできる場所ですが、同時に誘惑が多く、集中がそれる因子に溢れている場所でもあります。
「リビングで10分だけ休憩」のはずが、気付くとお菓子を食べながらダラダラテレビやスマートフォンで時間を溶かしてしまったり、「ちょっとストレッチしよう」と寝転がったソファでうっかり眠ってしまったり。
そんな「やってしまった!」を避けるために、図書館や塾の自習室、学生に解放されている公共スペースなどを活用してはいかがでしょうか。
スケジュール管理を見直す
スケジュールを細分化する
「9:00〜9:45 数学の問題集」「22:45〜23:00 英単語暗記」のように時間を細かく区切って勉強の計画を立てることで、やるべきことが明確になり、その結果集中力が高まります。
休憩を取り入れる
自分が「今集中出来てるから、このまま行けるとこまでやり続けよう」と思っていても、人間が集中できる時間は45分程度、深く集中できるとなると15分程度です。
それを超えてダラダラ勉強しても無駄な時間が流れるだけで、生産性はあがりません。
あらかじめスケジュールには休憩時間を組み込み、適切な休息を取りましょう。
優先順位を明確にする
やるべきタスクをリストアップし、優先順位をつけることで重要なことに集中出来ます。
「今すぐ取り組むべきこと」「後回しにできること」を区別し、効率的に勉強することで、集中力がグンとアップします。
デジタルツールを利用する
スケジュール管理にはアプリやカレンダーを利用すると便利です。to doリストを作成すると、やるべきことが「見えるか」でき、計画通りに進めやすくなります。
モチベーションを高める
目標を明確化し、成功体験を積む
自分がどうなりたいかという将来のビジョンを考え、進学先や将来の方向性を決めましょう。
とはいえ、アクセスできる情報に限界があるのも事実です。
自分一人で思い悩まず、学校の進路指導の先生や塾の進路コーディーネーターに相談してみることをお勧めします。
やるべきことが明確化したら、次に達成できる目標を設定し、成功体験を積むことで集中力がアップします。
体調管理を徹底する
睡眠と食事を見直す
睡眠不足は集中力低下の大きな原因です。
受験生は夜遅くまで塾に通ったりと、どうしても睡眠が疎かになってしまいますが、受験本番で最高のパフォーマンスが発揮できるように、日頃から最低でも7時間の睡眠時間を確保し、体調を整えておきましょう。
また、脳の働きをサポートするためにも、ビタミンB群やオメガ3脂肪酸の摂取を意識し、栄養バランスの取れた食事を心がけることも重要です。
「食べる」「寝る」「運動する」という基本的な活動を規則正しく行うことで健康な体と心を維持でき、受験勉強のパフォーマンス向上に繋がります。
室温や家具を再検討する
勉強をしていても、部屋が暑すぎる・寒すぎる・湿気でジメジメする、などで、いまいち捗らないといった経験はありませんか?
不快な環境下で一定時間作業を行うと疲労してしまい、その結果、覚醒度や注意力が低下してしまうことがわかっています。
例えば、室温が高い状況に長くいると人間の脳や内臓など体の内部の体温、つまり深部体温が上昇します。
脳の温度が上昇すると、情報処理能力が低下し、注意力が散漫になってしまうのです。
環境省のホームページでは、省エネの観点から「夏季28℃、冬季20℃」の温度設定が推奨されていますが、実際は快適と感じる温度は人それぞれ。
自分の快適と感じる室温を見つけ、集中できる環境を整えましょう。
また、机や椅子は自分にあったものを用意したり、高さや角度を調節し、クッションや自分に合った文房具を試すなど、ちょっとした工夫でより集中でき、パフォーマンス向上に繋がることもあります。
ぜひチェックしてみてください。
参考URL:「暑さで集中力が低下する」日本医事新報社
参考URL:「家庭のエネルギー事情を知る」環境省
シングルタスクを意識する
どんなに勉強しても、受験が近づくにつれ、「〇〇もやらなきゃ!」「〇〇がまだできていない!」と焦ってしまい、あれもこれもと手をつけたくなる気持ち、よくわかります。
しかし、マルチタスクはその複雑さから生産性が低下し、エラーが増加、その結果がストレスを招くという負のスパイラルに陥ってしまうのです。
そうならないためにも、タスクを整理し、優先順位の高いシングルタスクから取り掛かりましょう。
人は誰しも「抽象的で未確定なタスク」を行うことに関しては非効率的となってしまいますが、「具体的で確定しているタスク」は効率的にこなしていくことが出来ます。
二兎追うものは一兎も得ず!
一見回り道に見えても、シングルタスクは一つのことに集中するため作業効率が高まり、集中力を持続させることができるのです。
まとめ
いかがでしたか?
「受験勉強に集中出来ない」という人は、まず出来ない原因は何かを探り、対処していくことが大切です。
どんなに頑張っても持続時間には限界がある集中力。
ぜひ自分に合う方法を見つけてみてください!