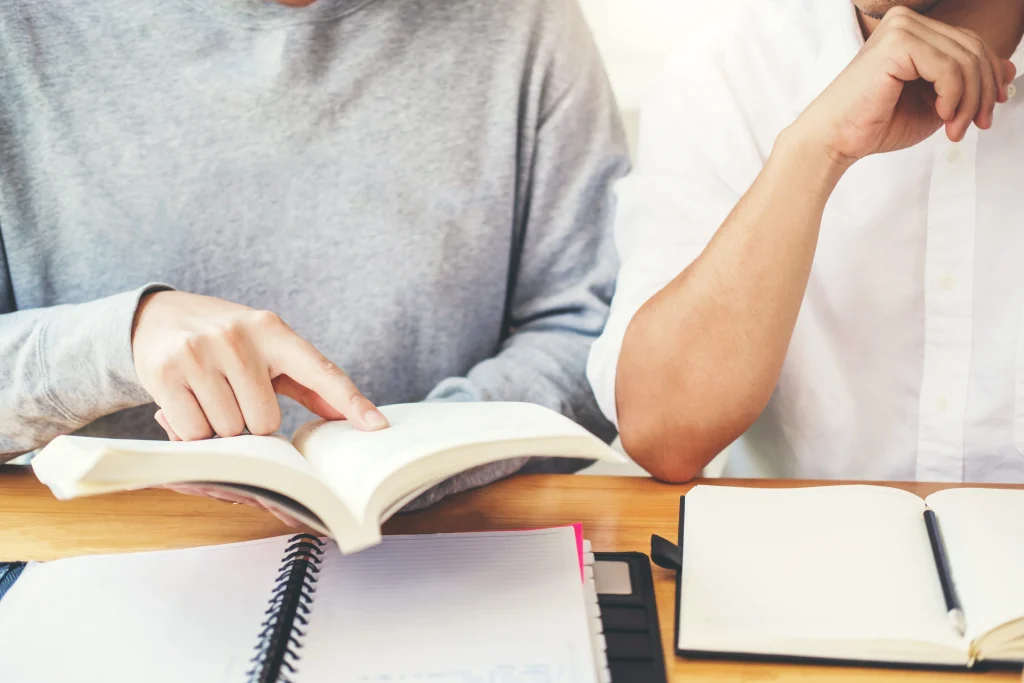大学受験は、親子で一緒に取り組んでいくものです。また、受験制度は時代によって変わっていくものであるため、親御さんが受験生であったころとは違うものになっていることもよくあります。受験を受けるお子さんは、もちろん、親御さんにもある程度受験に関する知識が求められます。そこでここでは受験生を控えるお子さんを持つ親御さんのために、「受験の種類・方法」「受験に使われるテストの種類」「子どもの受験に際して、保護者が気を付ける注意点」について解説していきます。
多種多様な受験の種類・方法
現在の大学受験のかたちは、下記の4つに分けられています。
- 国公立大学の一般選別
- 私立大学の一般選別
- 総合型選抜
- 推薦型
それぞれその特徴と必要となる試験について解説していきます。
国公立大学の一般選抜
まず、もっともイメージしやすいであろう「国公立大学の一般選別」から解説していきます。
これは、まず共通テスト(「大学入学共通テスト」。「共テ」とも呼ばれる。下記では「共通テスト」の表記に統一する。
6教科から成る試験であり、日本最大規模の試験のこと。試験の内容については、詳しくは後述)を受けるところから始まります。
そして共通テストののち、各大学で設けている個別試験を受けます。
個別試験の内容や教科は大学によって異なりますが、1教科~4教科が基本となります。
共通試験+個別試験をあわせて合否が判定されるのが国公立大学の受験の特徴ですが、それ以外の特徴として、「受験可能な回数が3回までと定められている」という点も押さえておかなければなりません。
また国公立大学の場合、「前期日程でA大学に合格して入学手続きをした場合、中期でB大学+後期でC大学を受験しても得点に関わらず合格扱いとはならない」という特徴があります。
そのため、中期・後期の受験は、「第一志望を前期に受けて、かつそれが不合格になったときに受けるもの」と考えておくべきです。
私立大学の一般選抜
多少の違いはあるものの、ある程度受験の形式が決まっている国公立大学とは異なり、私立大学の一般選別の形式は多種多様です。
大学によって、
- 共通テストの成績のみで、合否判定を行う
- 大学が独自に設ける個別試験のみで、合否判定を行う
- 共通テスト+個別試験を併用して、合否判定を行う
などのように、さまざまな受験方式および合否判定形式があります。
また、私立大学の一般選別の場合、同じ大学・学部で、複数の受験形式をとっているところが非常に多いといえます。
「どうしてもこの学校の、この学部に入りたい!」ということであれば、再度別の日程(後期試験など)でチャレンジすることもできます。
加えて国公立大学とは異なり、スケジュールさえ調整できれば、何度でも、何校でも受験が可能です。
総合型選抜
総合型選抜は、かつてAO入試(Admission office)と呼ばれていたものです。
これは、「大学側・学科および学部側が提示する、望ましい学生像に合致しているかどうか」を合格の基準とするものです。
たとえば早稲田大学の創造理工学部 早稲田建築AO入試では、下記のような方針を取っています。
“創造理工学部の建築学科において、創造性豊かで指導力に富み、率先してチームをまとめ上げるコミュニケーション能力に優れた活発な学生を求める入試制度です。
―引用:早稲田大学入学センター「For undergraduates」
https://www.waseda.jp/inst/admission/undergraduate/system/ao/”
AO入試のときに用いられる受験方法は、大学によって異なります。
ただ、「自校が求める学生を採る」というやり方であるため、書類審査は課せられるものと考えてよいでしょう。
また、小論文や面接が行われることもあります。
共通テストの実施の有無は大学によって異なり、非常に厳しい審査基準を設けているところもあれば、共通テストを課さないところもあります。
なお、「共通テストを課すか課さないか」は、大学のレベルによって決められるのではなく、大学ごとの方針によって異なります。
推薦型
推薦型とは、基本的には高校側(※例外あり)から「この生徒は高校時代に活躍していて、大学に入ってからも十分な活躍が見込めます」と担保されて大学に送り出される形式を指します。
この推薦型は、主に下記に分けられます。
- 学校推薦のうちのひとつ「公募推薦」……高校時代の成績や、ボランティアなどの活動を評価した高校側が、「この人物なら推薦に足る」と判断する生徒を大学に推薦する制度です。大学が求める成績をクリアしていれば受けられるものは特に「公募制一般推薦」と呼ばれ、文化活動や持っている資格などを条件とする「公募制特別推薦選抜」に分類されることもあります(なお後者の「スポーツ推薦」も、「公募制特別推薦選抜」のうちの一種です)。
- 学校推薦のうちのひとつ「指定校推薦」……公募推薦と同じく学校推薦に分類されるものですが、公募推薦の場合は「高校から推薦を受けることができれば、どこの大学でも対象となり得る」という性質を持っているのに対し、指定校推薦は「大学側は、自校の指定した高校からのみの推薦しか受け付けない」という特徴があります。そのため、自分の通っている高校が大学から推薦校として指定されていなければ、これを受けることができません。
- スポーツ推薦……スポーツ(部活動)で格別の成績を残した生徒が受けられるものであり、大学でもそのスポーツを続けていくことを前提となる推薦型です。
基本的には学校推薦の形態をとりますが、「外部のクラブチームで活躍していて、そこの監督などが推薦した場合は、スポーツ推薦の対象となり得る」としている大学も多くあります。
※大学在学中に不幸にも途中でけがをして競技が続けられなくなった場合であっても、それを理由として退学などを迫られることはありません。
推薦はしばしば、「成績は悪くても構わない」「試験はない」と誤解されがちです。
しかし実際には高校時代の成績が非常に悪ければ推薦を獲得できませんし、受験時に試験が課せられる学校もあります。
なお、面接はほぼ確実に実施されるため、これの対策は必須です。
加えて、大学側は「高校側が担保した人材を自校に招き入れる」というスタンスを取るため、推薦された生徒の入学後の素行や成績が著しく悪かった場合は、「もうこの高校からの推薦は受け入れない」となってしまうこともあります。
つまり、自分だけでなく後輩の道をも閉ざすことになってしまう場合もあるわけです。
また、推薦を勝ち取るときの競争率は高く、大学の選択肢も狭まりがちです。
ただ、推薦を勝ち取りさえすれば高い確率で志望校に合格できるうえ、早い段階で進路が決まるというメリットがあります。また一部の推薦枠の場合、学費が減免される場合もあります。
受験のときに使われるテストの種類
上では受験の方法とそのときに必要なテストについて簡単に解説してきましたが、ここからはそのテストの内容についてより詳しく解説していきます。
ここで取り上げるのは、
- 共通テスト
- 個別試験
- 英語4技能試験
- 小論文
- 面接
です。
共通テスト【国公立一般選別】【私立一般選別】
かつて「大学入学センター試験(1990年~2020年)」と呼ばれていたものであり、1月中に土日の2日間をかけて行われるテストです(2024年は1月13日と1月14日)
毎年50万近い人が受けるテストであり、日本で最も大きい規模のテストです。
教科は数え方によって異なりますが、「6教科」あるいは「7教科」とされることが多いといえます。
- 国語
- 外国語
- 理科
- 数学
- 情報
- 社会(地理歴史/公民。地理歴史と公民を分けて、「7教科」と換算することもある)。
なお「地理歴史」のなかには日本史と世界史がともに含まれます。また「公民」のなかには政治・経済と倫理も含まれます。
外国語は一般的には英語が選択されますが、ドイツ語やフランス語、韓国語や中国語も選択できます。
特定の国からの帰国子女や、子どものころからいずれかの言語を学んでいた、あるいはルーツや家庭に各言語話者を持つお子さんの場合は、英語以外も選択肢となるでしょう。
「理科」は、教科としては1つにまとめられていますが、そのなかで「物理」「科学」「生物」「地学」などに分けられています。
また数学も、「数学I」「数学A」「数学Ⅱ」「数学B」「数学C」に分けられています。数学において非常に特徴的なのは、「数学Ⅲ」は共通テストの教科としてはない、ということです。ただし理系大学を受ける場合、個別試験(※後述)で必要になることがあります。
共通テストは、国公立の一般選別を受けることが前提となります。
総合選抜の場合は大学によって異なり、共通テストの受験を必要としないところもあれば、必要とするところもあります。
個別試験【私立一般選別】【国公立一般選別】
個別試験は、その大学独自のテストのことをいいます。
3教科での受験がよく見られますが、1~2教科で受けられることもあります。
また、「国語が教科に入っているが、古文や漢文は出題せず」としているところもあります。
また、共通テストで教科に入っていない「数学Ⅲ」は、理系の大学(理工学部や工学部・理学部、医学部など)では個別試験としてその学力を確認される場合があります。
共通テストでも過去問を解くことが必要となりますが、個別試験の場合は特に「志望校の」過去問に積極的に取り組む必要があるでしょう。
また学校・学部・学科によって必要とされる教科・科目が大きく異なるので、しっかり確認しておくことが必要です。
英語4技能試験【大学により異なる】
英語4技能試験とは、「英語の能力である、スピーキング・ライティング・リーディング・リスニングの4技能において、十分な力を持っていると客観的に判断される場合、それをテストの点数および条件として加味する」という制度です。
この英語4技能試験の客観的判断の指標とされるものとして、「実用英語技能検定(基本2級以上だが、得点や大学によっては準2級も対象となりうる)」「TOEIC®」「ケンブリッジ英語検定」などが挙げられます。
この英語4技能試験の取り扱いは、大学・学部・学科によって異なります。
たとえば立命館の国際関係学部国際関係学科グローバル・スタディーズ専攻の場合は「IR方式(英語資格試験利用型)」として、「英検などで一定の級・点数を取っている者のみから出願を受け付ける」としています。
また、明治大学などでは、「英語4技能試験は利用できるが、これを利用しない入試方式もある」としています。
さらに、九州大学では、「英検などで高い成績を修めている者に関しては、共通テストの英語の得点を満点として扱う」という措置がなされていました(2025年まで、2026年からはまた換算方法が変更になる)。
英語4技能試験は、「あらゆる大学で実施されている」というものではありません。
ただ、英語関係の資格を取得している人にとっては、優遇が受けやすく、非常に有利になりやすい試験方法だといえます。
なお英語関係の検定については、「過去2年間以内に取得したもののみを対象とする」などの基準を設けているところもあるので、確認しておきましょう。
小論文【推薦】【総合選抜】
「小論文」は、推薦型や総合選抜で必要になることが多いものです。
その内容は学校・年・学部学科によって異なり、受験生の倫理観を問うものから、「短い文章で簡潔にテーマを説明せよ」としてくるもの、またグラフなどの分析を求めるものなど、多岐にわたっています。
小論文は、一般的なテストとは異なり、明確な「正解」がありません。
またある程度文章を書き慣れていないと、突破することは不可能です。
そのため、普段から文章を作る練習をある程度積んでおく必要があります。
また小論文は、序論→本論→結論 の順番で書いていくものであり、学校で課せられる「読書感想文」などとは本質的にその性質が異なります。
推薦や総合選抜の場合であっても、小論文の出来が著しく悪い場合は、当然試験に不合格となってしまうケースもあります。
面接【推薦】【総合選抜】
一般的なテストだけで合否を測る受験形式とは異なり、推薦型や総合選抜型ではほぼ「面接」が必須になります。
面接では、「高校時代に打ち込んでいたことは何か」「将来の進路をどう考えているか」「(なぜほかの学校の同学部ではなく)うちの大学を志望したのか」などが聞かれます。
面接は、小論文以上に「答えのないもの」です。
ただ、ほかの学校との差別化が問われる「なぜうちの大学を志望したのか」に関してはその学校の教育方針などを踏まえたうえでの解答が望ましいとされていますし、進路は過去や現在の自分を起点としてもの将来を語れるとより好印象となるでしょう。
また面接においては、「面接官多数で、お子さんが1人」という状況になるのが基本です。
この点は、ほかの試験方法と大きく違う点です。そのため、「緊張」という大きな敵を制する必要があります。
塾や学校で面接の練習をしっかり行い、当日にしっかり答えられるように訓練しておかなければなりません。
子どもの受験に際して気を付けたいこと
最後に、子どもの受験に際して知っておきたい注意点について紹介していきます。
国公立は最大3回まで、私立大大学は無制限で受けられる
国公立大学の受験回数は、前期―中期―後期の、最大3回です。
また入学手続きをしてしまうと、それ以外の学校に入ることは原則できません。
そのため、「第一志望は前期に受ける」「第二志望以降もしっかり事前に考えておくこと」が重要です。
対して私立大学の場合は、回数無制限で受けられます。
しかし受験にかかる費用は決して安くありませんし(後述します)、試験日がダブルブッキングする可能性もあります。
そのため、計画的に受験計画を立てる必要があります。
大学受験にかかる費用の平均値は私大の場合は25万円以上! 自宅外通学の場合は初年度の支払額が230万円超え
子どもは受験突破のための勉強のことだけを考えていればよいのですが、親御さんはそこに加えて、「費用」のことも考えなければなりません。
東京私大教連が出したデータでは、なんと私大受験にかかる費用は25万円~26万円となっています。
これは「受験するためにかかる費用だけ」の算出であり、実際に入学となればもっと大きなお金が動きます。
初年度に払う費用は、自宅外通学(家賃などが必要になる)の場合、初年度の授業料も含めてなんと200万円越え、上記の「25万円~26万円」と合わせると、実に230万円以上の出費となります。
自宅通学の場合は家賃などの出費が不要となるため、初年度の授業料137万円+受験費用25万円~26万円で160万円程度に収まりますが、それでもかなり大きい数字だといえます。
現在の1世帯あたりの平均年収は524万円、中央値が405万円ですから、実に年収の2分の1~3分の1がこの受験時に出ていくことになります。
そのため、受験生を抱える(抱えることになる)ご家庭では、受験のときに向けて、資産計画を立てる必要があります。
なお、国公立大学の場合は大きく出費が抑えられます。
受験料は平均で17000円ですし、入学金は28万年程度、年間の授業料も54万円程度とされています。たとえ一人暮らしをする場合であっても、その出費は、私大に進む場合に比べて3分の1~4分の1程度で済みます。
出典:
厚生労働省「2023年(令和5)年国民生活基礎調査の概況」p10
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/dl/10.pdf
東京私大教連「私立大学新入生の家計負担調査」
http://tfpu.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/20240405kakeihutanntyousa2023-1.pdf p7
北陸銀行「国立大学の学費はどれくらい?卒業までの総額や学部別、私立との違いを比較」
https://www.hokugin.co.jp/cs/loan/gakushi/contents/001.html
子どもに寄り添うことが何より大切
受験のときは、お子さんは非常に神経質になるものです。
そのため、親御さんにはお子さんに寄り添う姿勢が求められます。
お子さんを信頼し、サポートし、うまくいかなかった場合には適切な慰めの言葉をかけて、受験を乗り越えていきましょう。
また、「親も一緒に勉強している姿」を見せることは、お子さんの勉強へのモチベーションをアップさせ、勉強の悩みを話しやすい環境を作ることに有効です。
お子さんの受験に合わせて、親御さんも、仕事の資格取得のための勉強に取り組んでみてはいかがでしょうか。
親御さんも無理をしないで! 相談できる場所があります
大学受験の合否は、それだけで人生の成功不成功を決定づけるものではありませんが、お子さんの人生において大きな分岐点となることは確かです。
そのため、親御さんも無理をしたり悩んだりしてしまうこともあるでしょう。
そんな親御さんは、学校の先生や塾の講師などにぜひ相談をしてください。
お子さんの前では見せることをためらう悩みも、「外部」の人間にならば打ち明けられることもあるかと思います。
受験生のお子さんが一人ではないように、親御さんもまたお一人ではありません。
「令和の受験知識」をつけて、受験を乗り越えましょう!
現在の受験の形式は、大きく「国公立大学の一般選別」「私立大学の一般選別」「総合型選抜」「推薦型」に分けられます。
また試験に使われるテストとしては、「共通テスト」「個別試験」「英語4技能試験」「小論文」「面接」があります。
どの方法を選ぶかで受験への取組が大きく変わってくるので、お子さんと話し合ってベストな選択肢を選ぶことが重要です。
私たちアクシブアカデミーでは、お子さん自身の悩みはもちろん、お子さんと並走する親御さんの悩み相談も受け付けています。
お子さんと親御さん、そして私たち、三人四脚で受験を乗り越えていきましょう!▶アクシブアカデミーの無料受験相談はこちらから!